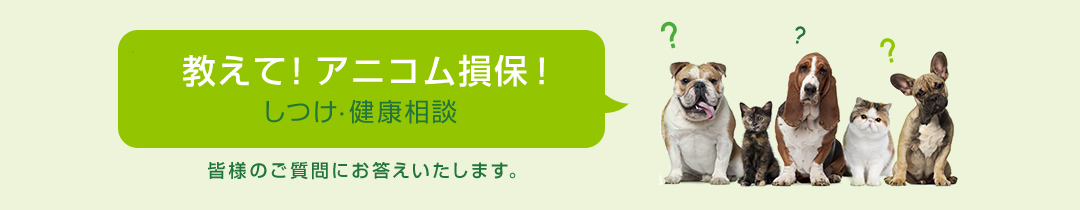���f���������p�̊F�l��
���ɋ������܂����A2021�N4��30���������܂��āA���f���̐V�K���e�̎�t���I���������܂����B
�ߋ��ɓ��e����������������y�щ͈��������������������܂��̂ŁA�u���[�h�����v�������p���������B
�Ȃ��A�A�j�R�����ۂł́A�ǂ��Ԃ���Ɩ��i�����Ă��߂��������������߂ɁA�ȉ��̃T�[�r�X�����p�ӂ��Ă���܂��B
���Ђ����p���������B
-
- ���݂�Ȃ̂ǂ��Ԃa�C��S��
-
�ǂ��Ԃ̂��ƂȂ�Ȃ�ł����܂����I�a�C�Ɛf�Ô�킩���僁�f�B�Ahttps://www.anicom-sompo.co.jp/doubutsu_pedia/
-
- ���ǂ��Ԃz�b�g���C��
-
�a�C�̂��ƁA�����̂��ƁA���N�̂��Ɓc�B�Ȃ�ł����C�y�ɂ����k���������Bhttps://www.anicom-sompo.co.jp/hotline/��t���ԁF10�F00�`17�F00�i�����̂݁j���A�j�R�����ۂ̂��_��Ґ�p�T�[�r�X�ł��B