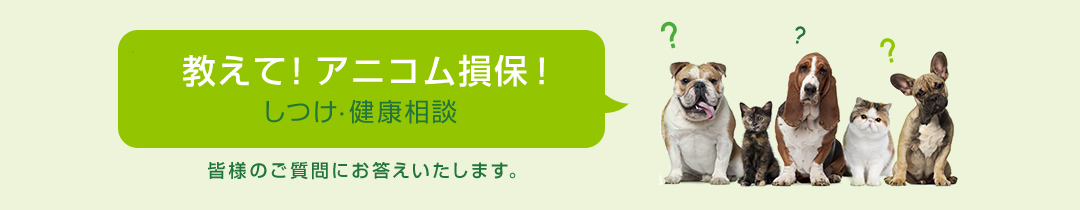10月で11歳になる雌のトイプードルです。避妊済みです。
2か月前から身体の動きの悪さ、震えなどがあり、椎間板ヘルニアを疑い二次医療機関にてMRI、CTでの検査を行ったところ背骨の数か所において組織破壊の形跡があることがわかりました。
針を刺して細胞診を行いましたが、異常といえる細胞は見つからず、腫瘍によるものか炎症によりものなのかの診断ができずにいます。
現在は、とりあえす安静に過ごし、定期的にレントゲンなどで病変が他に広がっていないかどうか経緯を見ていくしかないといわれています。
飼い主としては、このまま様子を見ていくしかないのかと思うと歯がゆくてたまりません。
炎症反応も悪化してきているので心配です。
今のところ食欲はありますが、あまり元気はありません。
東洋医学でもサプリメントでも、何か打つ手があれば取り入れたいと思っています。
アドバイスいただけたら幸甚です。
Re: 背骨の組織破壊
- 獣医師 酒井
2015/09/28(Mon) 15:06
No.4145
ななとさくら 様
10月も近づき、秋の気配が日々深まっていることを感じる今日この頃でございますが、
ななとさくら様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
この度はご相談をいただきまして誠にありがとうございます。
早速ご案内させていただきますが、実際のワンちゃんのご様子を拝見して
おりませんので、一般的なご案内となりますことをご了承下さい。
ななとさくら様の10歳の女の子のトイプードルちゃんが2ヶ月前から、震えがあり、
身体の動きも悪くなって、検査を受けたということでございますね。
今のところ確定診断がつかず、経過観察中ということで、積極的な治療ができないため、
何か他の東洋医学やサプリメントなどの代替医療で、トイプードルちゃんにしてあげられることが
ないかというご相談でございますね。
一般的に動物病院で広く行われている、西洋医学に基づく治療は、身体の中の悪い部分に
注目し、その病変に対して、科学的に効果が立証されている方法(エビデンス)に従って行います。
ななとさくら様のトイプードルちゃんの場合、画像診断によって背骨の組織破壊が認められ、
その原因を調べるために細胞診をしたということでしたが、腫瘍か炎症か判断がつかず、
確定診断に至らなかったということでございますね。
西洋医学では、もし背骨の組織破壊が腫瘍と診断された場合には、抗がん剤や
放射線療法などの治療を行い、炎症と診断された場合にはウイルスや細菌などによる感染性の
炎症か、非感染性の炎症かによって治療方法が異なりますので、正確な確定診断のためには
MRIなどの画像診断に加えて、脳脊髄検査など一歩踏み込んだ検査が必要になる場合も
あります。また脳脊髄の病気の中には、脳や脊髄の病理組織検査が不可欠のものもありますが、
脳や脊髄の検査には困難が伴う、あるいは検査ができない場合もありますので、
診断そのものが難しいケースも多いかと存じます。
診断自体が困難な場合には、治療方法も定まらないため、一定期間毎に検査を行いながら、
経過を見ていくことがあります。またその病気をダイレクトにたたく治療は選択できない状況でも、
今あるワンちゃんの不快な症状を改善させることを目的として行う治療もあります。
例えば食欲がない場合に食欲増進剤を使用したり、痛みがあって辛い場合に消炎鎮痛剤を
使用するといった治療方法です。こういった治療法を対症療法と言います。
病気の原因がはっきりしていないので、この対症療法を行うことによって、思ってもいない副作用
があることも考えられますが、ワンちゃんのQOL(生活の質)を改善するという意味では、
状況によっては積極的に取り入れていくことが望ましい場合もあります。
今、ななとさくら様のトイプードルちゃんは、食欲はあるけれども、あまり元気がないということで
ございますね。元気がないというのは、具体的には、どこか痛みがあるようでしたり、神経的な
麻痺があるような症状があるのでしょうか。貧血や脱水など一般状態はいかがでしょうか。
何か対症療法を行うことで、トイプードルちゃんの元気を回復できる方法がないか、
まずはかかりつけの先生にご相談なさってみてはいかがでしょうか。
また西洋医学以外の東洋医学やサプリメントなどは、代替医療とよばれており、漢方薬による
治療、鍼灸治療、ホメオパシー治療やオゾン療法、アロマテラピーなどもこれに含まれます。
病変部自体に注目するというよりは、身体全体の自然の治癒力を高めるという考え方で
行われる療法です。科学的に立証されたエビデンスに基づいたものではありませんが、
過去の経験から効果が期待されて難治性の病気や、西洋医学による治療では良好な
効果が認められないケースで利用されていることが多いようです。
近年では西洋医学に加えてホメオパシー治療、オゾン療法などの代替医療を積極的に
取り入れている動物病院もございます。
私どもでは、その治療効果の良し悪しを判断するデータは持ち合わせてはおりませんので
具体的に個々の代替医療をお勧めすることはできませんが、西洋医学では治療が困難という
場合に、代替医療を実施されている先生にご相談いただき、ななとさくら様がご納得できる
治療方法があれば取り入れてみて、トイプードルちゃんの体調が改善するかどうかご覧になるのも
一つの方法かと存じます。
たとえば、悪性の腫瘍などでは免疫のバランスを整える効果が期待されるサプリメントなどが、
特殊な動物病院ではなく一般の動物病院でも広く取り扱われています。
一度かかりつけの先生に、そういったサプリメントの使用についてもご相談いただくと
良いかもしれません。
なお、アニコムでは下記の受付時間で、ご契約者様からのお電話での
健康相談、しつけ相談サービスを承っておりますので、ぜひご利用ください。
お電話番号は、あんしんサービスセンター0800-888-8256です。
平日9:30~17:30 / 土日・祝日9:30~15:30 (年末年始を除く)
土日・祝日は予約のみ、実際のご相談は翌営業日以降となります。
トイプードルちゃんが少しでも元気を取り戻し、ご家族の皆様と楽しく過ごせますよう、
いつも応援致しております。
今後ともアニコムを宜しくお願い申し上げます。
Re: 背骨の組織破壊
- ななとさくら
2015/09/29(Tue) 21:30
No.4148
酒井先生
わかりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
この一週間の間に旺盛だった食欲が減ってきたようです。
家族が帰宅した時など嬉しいはずの瞬間も起きてこないことも多く、どこか調子が悪いのだろうなという印象を受けます。
主治医と相談しながら見守っていきたいと思います。
Re: 背骨の組織破壊
- 獣医師 酒井
2015/09/30(Wed) 13:08
No.4150
ななとさくら様
この度はご丁寧にご返信いただき誠にありがとうございます。
トイプードルちゃんの食欲が落ちてしまったり、ご家族のご帰宅時に元気な姿を見せてくれないと、
本当にご心配ですね。
主治医の先生ともご相談いただきながらケアしていただき、トイプードルちゃんが大好きな
ご家族とご一緒に笑顔で過ごせるように、心から応援いたしております。
また何かご心配なことがございましたら、いつでもお気軽にお声掛けください。
今後ともアニコムをどうぞよろしくお願い致します。
Re: 背骨の組織破壊
- ななとさくら
2016/09/08(Thu) 14:41
No.4474
前回相談させていただいた折はありがとうございました。
その後の経過ですが
脂肪織炎(化膿性肉芽腫)ではないかとの疑いのもと、ステロイドの投与をを8か月ほど続けました。
ステロイドによく反応しCT画像上は背骨の組織破壊は残っているものの、元通りの元気を取り戻したため、治療はいったん終了となりました。
その後2か月ほど経過した頃、体表面に1センチほどのしこりを発見し、もしや脂肪織炎の再発ではと思って細胞診をしてもらったところ、前回と同じ(マクロファージの出現)という結果が出ました。
外見上はしこりから膿が出ていることはなく、発熱、元気の消失もないため、とりあえず様子を見ることになっていますが、わかりにくい病気で心配です。
お伺いしたいのは
①元気があるようにみえても炎症反応が悪化していることはありますか?
炎症反応を定期的に検査するのは意味のないことでしょうか。
②膿が体の内部に出て重篤な状態になることは考えられますか?
以上ご回答お願いいたします。
Re: 背骨の組織破壊
- 獣医師 霍田
2016/09/12(Mon) 17:51
No.4479
ななとさくら 様
風の中に秋を少しずつ感じるようになってまいりましたが、ななとさくら様におかれましては
いかがお過ごしでしょうか。
この度はご相談をいただきまして誠にありがとうございます。
ご相談についてご案内いたしますが、実際のご様子を拝見しておりませんので、
一般的なご案内となりますことをご了承ください。
以前いただいたご相談の、その後の経過に関してのご質問でございますね。
脂肪織炎を疑いステロイドの投薬を続け、元気を取り戻してくれたものの、2ヶ月ほど経過してから
体表面にしこりが見つかり、経過を観察することになったのですね。
ななとさくら様のご心配はいかばかりかと、心中お察し致します。
皮膚の下には、皮下脂肪といわれる皮下脂肪(組)織があり、体を衝撃などから保護しています。
脂肪織炎は、何らかの原因でこの脂肪織に炎症が起こる疾患です。
皮下以外にも脂肪織はあるので、皮膚以外でも起こることがあります。
脂肪織炎は、主に胸やおなか、脇腹や背中などの体幹部に発症するといわれ、
発熱する症例もみられます。
はじめは小さなしこりが腫れて大きくなり、しこりの中央部分が突出してやがて穴があき、
膿が出ることがあります。そのままにしておくと穴の部分から細菌感染などを起こし、
炎症が脂肪織下の骨や筋肉などに広がると、重篤な状態になることも考えられます。
脂肪織炎の原因には様々なものがありますが、細菌や真菌などの感染によって
引き起こされる「感染性脂肪織炎」と、細菌などの感染がない「無菌性脂肪織炎」に大別されます。
(1)感染性脂肪織炎
感染性脂肪織炎は、細菌や真菌が脂肪織に感染して発症するため、例えば何らかの外傷が皮下に
達して炎症を起こしたり、皮膚のしこりが化膿して、皮下まで炎症が波及したりすることでも起こります。
このような場合には、患部が体の一部に限局(限定)していることが多いとされます。
しかし、どうぶつの体調がよくなかったり、基礎疾患などがあり免疫力が低下しているなどの要因が
あれば、あちこちに広がってみられる可能性もあります。
(2)無菌性脂肪織炎
自分自身の免疫システムが、何らかの原因で脂肪織を異物とみなして攻撃していると考えられる
「免疫介在性」の疾患が考えられます。
ミニチュア・ダックスフンドに多いとされているので、疾患の発症を促す誘発遺伝子がある可能性が
考えられており、この場合には体のあちこちに発症することがあります。
その他には、何かの手術をした後、関連部位に無菌性脂肪織炎が発症するケースも多いと
されています。この場合、皮膚の縫合に使用した糸が、アレルギー反応のような悪影響を脂肪織に
与えているのではないかと推察されています。
また、皮下注射した後、接種部位に発症する場合もあります。
次にななとさくら様からいただいた2つのご質問についてご案内いたします。
まず、最初のご質問ですが、ワンちゃんの性格などによっては体調に不調があっても、ぎりぎりまで我慢して
元気にふるまう子もいますので、外見上元気に見えても病状が悪化しているという可能性はあります。
そのため、日頃からトイプードルちゃんの様子をよく観察していただき、病院で定期的な検査を行うことは
とても大切なことです。炎症反応の検査については、かかりつけの先生とご相談の上、必要に応じて
実施なさるとよいと思います。
次に2つめのご質問についてですが、「しこり内に膿が貯留した場合、体内に排膿されて重篤な
症状が出る可能性は」という理解でよろしいでしょうか。
体内へ排膿されて症状をあらわすかは、そのしこりがどのような状況で、どういった由来で発生した
ものかによっても異なってくるかと思います。
ななとさくら様のトイプードルちゃんは避妊手術をされているのですね。
例えば、上述したような、何らかの手術の縫合糸が原因でしこりができている場合には、
体内の糸が残っている箇所と、体表のしこりの箇所が瘻管(ろうかん)という管で繋がって
いることが考えられます。そのような場合には、体の内部に膿が漏れ出てしまい、その結果として
重大な症状を引き起こしてしまう可能性も考えられます。
まだ小さなしこりで、今回の細胞診で確定診断はついていないかと思いますので、
もちろん手術などとは無関係で、体表に限局している腫瘤の可能性もあります。
トイプードルちゃんの様子やしこりの大きさなどに変化がないか観察していただき、
今後の治療方針についても、かかりつけの先生とよくご相談いただければと思います。
なお、アニコムでは下記の受付時間で、ご契約者様からのお電話での
健康相談、しつけ相談サービスを承っておりますので、ぜひご利用ください。
お電話番号は、あんしんサービスセンター0800-888-8256です。
平日9:30~17:30 / 土日・祝日9:30~15:30 (年末年始を除く)
土日・祝日は予約のみ、実際のご相談は翌営業日以降となります。
ななとさくら様とトイプードルちゃんが、心穏やかにお元気に過ごされますよう、
お祈り申し上げます。
今後ともアニコムを宜しくお願い申し上げます。
Re: 背骨の組織破壊
- ななとさくら
2016/09/16(Fri) 19:10
No.4494
このたびも詳細なご回答をありがとうございました。
また何か疑問に思うことが出てくれば質問させていただきます。
Re: 背骨の組織破壊
- 獣医師 霍田
2016/09/20(Tue) 14:57
No.4495
ななとさくら 様
こちらこそ、ご丁寧に恐れ入ります。
ななとさくら様とトイプードルちゃんをいつも応援いたしております。
ご不明な点などがおありの際には、お気軽にお声がけください。
季節の変わり目のため体調管理が難しい時期でございますので、
くれぐれもお体ご自愛ください。
今後ともアニコムをどうぞよろしくお願いいたします。