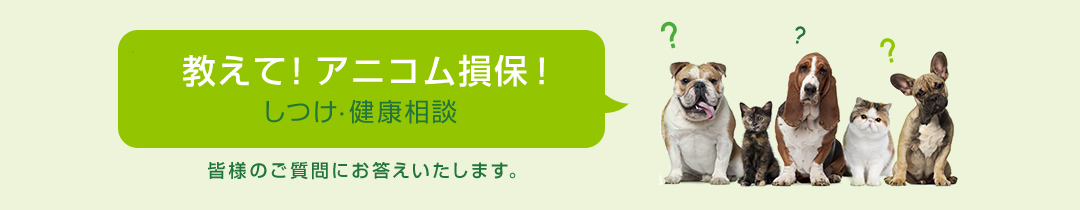当掲示板をご利用の皆様へ
誠に恐れ入りますが、2021年4月30日をもちまして、当掲示板の新規投稿の受付を終了いたしました。
過去に投稿いただいたご質問及び回答は引き続きご覧いただけますので、「ワード検索」をご利用ください。
なお、アニコム損保では、どうぶつさんと末永くあんしんしてお過ごしいただくために、以下のサービスをご用意しております。
ぜひご利用ください。
-
- ■みんなのどうぶつ病気大百科
-
どうぶつのことならなんでもおまかせ!病気と診療費がわかる専門メディアhttps://www.anicom-sompo.co.jp/doubutsu_pedia/
-
- ■どうぶつホットライン
-
病気のこと、しつけのこと、健康のこと…。なんでもお気軽にご相談ください。https://www.anicom-sompo.co.jp/hotline/受付時間:10:00~17:00(平日のみ)※アニコム損保のご契約者専用サービスです。