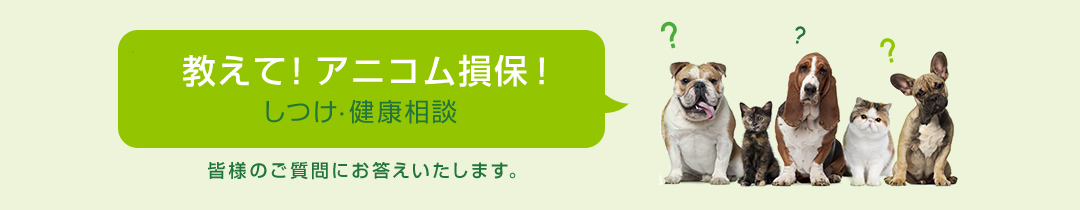肩・首の下・太ももの3カ所に盛り上がったかさぶたを見つけ病院に行きました。
爪などでばい菌が入り炎症を起こしているか真菌かも、とのことで
菌を培養しつつ受診日から真菌薬と抗生剤を2週間飲みました。
2週間後培地は赤になりましたが顕微鏡で胞子は確認できませんでした。
ウッド灯でも光りませんでした。
しかし患部が3箇所あることからもう2週間真菌薬を飲むことになり
今日で16日飲んでいます。
患部は広がったり脱毛したりせず
うちは猫2匹飼いで隔離してない状態で一緒にいますが
猫にも人にも移る気配はありません。
あと12日真菌薬を飲むことは納得していますが
培地が赤になったら必ず真菌症なのでしょうか。
また絶対真菌だと確定する方法は培養以外にないのでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 猫カビについて
- ニャン吉
2018/05/16(Wed) 16:32
No.5281
すみません、補足です。
生れてから病院とペット美容室以外一度も外に出たことがない猫です。
家には観葉植物や花などはいっさい持ち込んでおりません。
掃除も欠かさず毎日しています。
Re: 猫カビについて
- 獣医師 柳原
2018/05/18(Fri) 16:47
No.5284
ニャン吉 様
この度は、ご相談をいただきまして、誠にありがとうございます。
ネコちゃんの皮膚の真菌症(皮膚糸状菌症)は、その多くがMicrospore canesの感染が原因と言われています。
この真菌は、症状のない健康などうぶつさんの被毛や人、土壌、家の中にも存在していることがあり、
それらと接触することによって感染します。
また、通常、若いどうぶつさんや何らかの病気やストレスなどで抵抗力が落ちている時に感染しやすくなります。
診断方法には、病変部の被毛の顕微鏡検査やウッド灯検査、培養検査があります。
顕微鏡検査で、胞子や菌糸が検出された場合には確定診断となりますが、検出されなかった場合でも、
皮膚糸状菌症を完全に除外することはできません。
ウッド灯検査では、Microspore canisが感染している被毛に紫外線を照射すると蛍光色に光るのですが、
その検出率は約半数と言われています。
培養検査では、培地が黄色から赤色に変化すると皮膚糸状菌陽性と判定されます。
治療は、抗真菌薬の内服や外用薬、抗真菌薬入りのシャンプーなどがあり、状態によっては併用されることもあります。
また、適切に治療をおこなっていても、完治するまでは数週間から数ヶ月かかることもあります。
今回、ニャン吉様のネコちゃんが、どこから感染したのかは確定できませんが、
培養検査の結果から、皮膚糸状菌が原因である可能性は高いと言えるでしょう。
今後、投薬を続けても皮膚の状態に変化がない場合や、症状が酷くなるような場合には、
皮膚糸状菌だけでなく、原因が複合的にある場合も考えられますので、
再度かかりつけの先生にご相談されることをお勧めします。
それでは、今後とも、アニコムをどうぞよろしくお願いいたします。
Re: 猫カビについて
- ニャン吉
2018/06/05(Tue) 23:34
No.5311
先生、先日は詳しいご回答ありがとうございました。
その後抗真菌薬を4週間飲み続け、肝臓に副作用が出る場合もあるとのことで
一度血液検査をしたところALTが基準値22~84のところ130でした。
患部はどこかわからないくらい良くなってはいましたが
あと2週間は飲んだ方が良いとかかりつけの先生のお言葉でした。
少し不安でしたので、この数値で飲んで大丈夫かお聞きしたところ
先生はお考えになって、パルス療法でと言って下さり
抗菌薬は3日飲んで4日休みを2週間と、肝臓のサプリ30日分を出して下さいました。
3日飲んで4日休んだその4日目(6/4です。ちょうど1週間目)の昼間、真っ黄色のおしっこをしました。
黄疸かと驚いて白目部分を見ると普通に白でしたが心配になったので病院に電話し
翌日(今日の6/5を指します)から最後の1週間分の真菌薬を飲み始めても大丈夫かたずねたら
心配だったらお休みして様子を見ていいとのお返事でしたので飲まなかったのですが
今日もすごい色のおしっこをし、尿だけ持って調べて頂くと異常であったため
その後猫を連れて病院へ行き血液検査をしました。
肝臓の数値は全て大幅に基準値を超え、特にALTは前回の130からたった1週間で952に跳ね上がっていました。
黄疸は基準値0.1~0.4のところ0.8です。
そして入院になりました。
つづく
Re: 猫カビについて
- ニャン吉
2018/06/05(Tue) 23:35
No.5312
つづき
かかりつけの先生から沢山のご説明を受けましたが気が動転してしまい全ては思い出すことができません。
室内飼いで、変なものを食べたということはないはずです。すごく気を付けています。
ただ気になるのが、これは病院でお話しし忘れたのですが
うちには階段の明り取りにガラスブロックを設置していて
何となく元気がないかもと考え始めたあたりから
ガラスブロックのガラスだか目地だかを良く舐めていました。
すこし食べる量は減っていましたがそれなりには食べていました。
6.1キロから1週間で5.9キロに減っています、ノルウェージャンのオス、2歳7カ月です。
4月は6.3キロでしたがダイエットしてまして5月中旬は6.1まで減っていました。
極端に食事制限はしていません。
柳原先生のお考えをお聞かせ願えないでしょうか。
ダイエットが悪かったのか・・・。
私へのお気遣いは無用ですので悪かったら悪いと言って下さい。
もう藁にもすがりたい心境です。
Re: 猫カビについて
- ニャン吉
2018/06/06(Wed) 18:23
No.5316
補足です
抗真菌薬を飲み始める前に
かかりつけの先生から肝臓への副作用のお話しがあったので
以前ALPが高めに出たことが何度もあったため血液検査をしていただいています。
その時はALPが若干高めではありましたが(38~165のところ190)
他に異常はありませんでした。
Re: 猫カビについて
- 獣医師 柳原
2018/06/08(Fri) 10:56
No.5317
ニャン吉 様
再度、ご相談いただきまして、誠にありがとうございます。
この度は、回答にお時間を要しましたこと、お詫び申し上げます。
さて、肝臓は、体の中でさまざまな働きを担っている重要な臓器ですが、沈黙の臓器ともいわれ、かなりの障害を受けてからでなければ症状があらわれません。
程度により異なりますが、肝機能低下が進むと、食欲不振や下痢、嘔吐、黄疸などの症状が多くみられます。
さらに重症になると、毒素(アンモニア)を体内で処理できないために、神経症状(肝性脳症)があらわれたり、命に関わることもあります。
また、太ったネコちゃんに絶食や無理なダイエットを行うことで、肝リピドーシス(脂肪肝)がみられることがあります。
これは肝臓に過剰な脂肪がたまるために、肝臓が正常に機能しなくなる病気です。
数日の絶食や食欲不振により、たんぱく質が不足した状態になると、体の中の脂肪代謝が阻害され、それが引き金となって発症することがありますが、適度なダイエットでなければ問題ないでしょう。
ネコちゃんが、壁や床を過度に舐める場合は、舌触りや感触もきっかけになりえますが、ストレスや栄養不足、体調不良や、神経症状としてそのような行動をとることがあります。
化学製品の中には、ネコちゃんにとって有害なものもありますので、ぜひ一度、材質等をご確認ください。
また、一部の抗真菌薬は肝毒性があるため注意が必要ですが、病気は複合的な原因で起こることが多く、直接的な原因を断定することが難しい場合もあります。
いずれにしても、まずは疑わしき原因の排除と、症状にあわせた治療が第一となります。
今後の治療方針については、各種検査の結果や状態によっても異なりますので、かかりつけの先生とよくご相談ください。
それでは、今後とも、アニコムをどうぞよろしくお願いいたします。