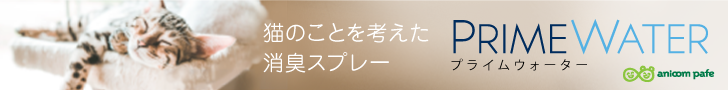猫と一緒に暮らすとき、一体なにを用意すればよいのでしょうか。猫を迎えるにあたって初日に必ず用意しておくべきグッズや家の中の準備、心構えなどについてもご紹介します。猫と上手に暮らしていくポイントをご紹介しますので、初めて猫と暮らす方はぜひ参考になさってくださいね。
初日までの準備 -グッズ編-
猫を迎えるまでに、どんなものをどのように備えておけばいいのかをご紹介します。
最低限、以下のものは用意しておきましょう。
- キャットフード
- 猫用食器
- トイレ
- 猫砂
トイレの準備
猫のトイレは、一般的にトイレ本体と「猫砂」と呼ばれる砂をセットにして使います。トイレ本体には、ノーマルタイプの他に、システムトイレやおまるなどがあります。
砂の種類は大きな粒から小さな粒まで何種類かあり、素材もさまざまです。いくつか試してみて、自分が飼っている猫の好みを確認しましょう。
システムトイレは、猫砂とボード状になったシートの二段式になっているものです。おしっこが一段目の猫砂を通過して二段目のボードに染みこむので、猫砂の汚れが少なく、衛生面で安心できるタイプといえます。
【関連リンク】
ネコちゃんのトイレのしつけ|みんなのどうぶつ病気大百科
寝床の準備
次に寝床についてですが、生後2ヶ月未満の子猫は、ケージの中で過ごさせるのがいちばん安全です。ケージの中に猫用ベッドを設置してあげましょう。
生後2ヶ月以上経っても、ひとりにさせるのが心配な場合は、飼い主が就寝中のときだけ、ケージの中に入れてあげるとよいでしょう。
大きくなると、猫によっては飼い主と一緒に寝る子もいます。冬はお互いがゆたんぽ代わりになるので、寒さも忘れてしまうしあわせなひとときが味わえます。ひとりで寝るのが好きな子には、落ち着いて休めるよう、明るすぎない場所にベッドを用意してあげましょう。
併せてそろえておきたいもの
- キャリーバッグ
- グルーミング用品
- 爪とぎ
- おもちゃ
- キャットタワー
病院に行くときや一緒に外出をするときにはキャリーバッグに入れて移動します。猫の身体の大きさに合ったサイズのキャリーバッグを選んであげましょう。万が一、災害にあった場合でも、避難をする際に必要となるので、ひとつは用意しておきましょう。
また、猫にも性格の違いがあり、人なつこい子もいれば、人見知りな子もいます。人見知りな子は、知らない人に会うことがストレスになるので、自宅に来客があるときは、あらかじめキャリーバッグにいれておいてあげるとよいでしょう。
グルーミングは、猫の毛球症や皮膚病予防のために行いたいケアのひとつ。小さな頃からグルーミングに慣れさせておくことが大切なので、まずはブラシやコームを用意して、遊びの中で慣れさせてあげましょう。
爪とぎには、カーペット、ダンボール、麻、木など、いろいろな種類があるので好みのものを見つけてあげましょう。市販のものを購入してもよいですし、飼い主が手作りしてもよいかもしれません。
好奇心旺盛で遊び好きの猫は、遊び道具のおもちゃが必需品です。追いかけたり、噛んだり、さまざまな種類のおもちゃが市販されているので、好みのおもちゃをいくつか選んであげましょう。
また、猫は上下運動を好むので、必要に応じてキャットタワーを用意してあげるのもいいでしょう。ただ、キャットタワーを用意してあげるのは、ある程度高いところに安心して上り下りできるようになってからにしましょう。高いところに登れても、落下する危険性があると思われる時期には、キャットタワーの設置は控えるようにしましょう。
【関連リンク】
ネコちゃんを迎える準備|みんなのどうぶつ病気大百科
初日までの準備 -お部屋編-
一緒に暮らす猫が快適に過ごせるよう、室内の環境を整えてあげましょう。何気ないものが猫にとってはとても危険だったりします。猫を守るための対策をご紹介します。また、猫の習性でもある爪とぎ対策についてもお話します。お気に入りの家具など、傷つけられたくないものは事前に工夫をしてきましょう。
危ないものを置かない
猫は思ってもいないものをおもちゃにして遊んだり、口にしたりします。たとえば電源コードは、猫がかじって遊ぶことが多いもののひとつです。かじっているうちに感電する危険があるので、コードカバーなどでコードを覆ってしまうなど、工夫をしましょう。
ビニール袋が好きな子もいます。かじっているうちに、食べてしまうこともあります。消化できないものを食べると、腸を傷つけることがあるので、口にして危ないと思う物は、棚の中にしまうなど、猫の生活圏に放置しないことが大切です。
【関連リンク】
異物誤飲|みんなのどうぶつ病気大百科
部屋を傷つけないために
猫には爪をとぐ習性があります。市販の爪とぎで満足する子もいれば、部屋の壁やドア、ふすま、ソファが好みの猫もいます。市販の爪とぎには目もくれず、革張りのソファをガリガリしたり、お気に入りの壁紙を楽しそうにザクザク引き裂いたり。あくまでも猫の習性なので、「やめなさい!」と叱るよりも、飼い主側で防止策を考えておきたいもの。
まず、最初に考えたいのが次のように爪とぎの置き方などを工夫してみることです。
- 家の中に数個所設置する。
- 猫の好みの材質のものにする(段ボール、麻、木など)。
- 爪とぎの向きを変えてみる(縦置き、横置き好みがある)。
- 床に直置きにするか、壁に立てかけるのか、好みを探ってみる。
いずれを試してみても、どうしても爪とぎをしてほしくない場所にしてしまう場合は、爪とぎをさせたくない場所に「保護シート」を張ったり、「爪とぎ防止スプレー」を吹きかける方法があります。匂いを嫌ってスプレーをかけた箇所に近づかなくなるので、爪とぎ防止に役立ちます。
【関連リンク】
ネコちゃんの爪のお手入れ|みんなのどうぶつ病気大百科
食事について

食事
猫は完全な肉食動物なので、健康を維持するために必要な栄養のバランスが、ヒトとも犬とも異なります。猫にとって必要な栄養がバランス良く含まれた食事を与えましょう。たいていの飼い主は、猫に必要な栄養素が含まれている市販の総合栄養食(キャットフード)などをライフステージ(成長段階)に合わせて与えています。
新鮮なお水は猫の健康維持にとって、とても重要なので、いつでも飲めるように用意してあげましょう。
食器は、フード用と飲み水用の、2種類の食器を用意します。猫がフードや水をこぼしてしまわないように、食器は安定感のあるものを選びましょう。また、食器の下にランチョンマットを敷くと、食べこぼしてもすぐに片付けられて便利です。
【関連記事】
子猫へのエサの与え方はどうする?適切な量は?
猫にも「しつけ」は必要?
猫にもしつけは必要なのでしょうか。犬にしつけはイメージがつきやすいですが、猫にしつけはイメージが付きにくい方も多いのでは? そんな猫ですが、猫も一緒に暮らす上でしつけをすることは大切なことです。困った行動を事前にコントロールできるようになると一緒に生活がしやすくなりますよ。
- 提案型しつけの必要性
- 小さな頃にいろいろなモノやヒトを見せてあげる
- 名前を呼ぶ
ひとつ屋根の下で一緒に暮らすにあたって、猫に対して「こうして欲しいな」と思うことが出てくるものです。こんなとき、どうやって教えていけばいいのでしょうか?
孤高のハンターである猫に、お互いにコミュニケーションを取りながら、人間と暮らすためのルールを教えるという犬流のしつけをすることは至難の業です。猫に「こうしたらどう?」という提案をうまくして、猫が望ましい行動をできるように仕向けていきましょう。
たとえば、「粗相をしないように使いやすいトイレを用意する」、「猫が戸惑わないように環境を一定にする」、「あちこちで爪をとがないようにあらかじめ好みに合いそうな爪とぎを何か所かに置いておく」など…。また、キャリーバッグに入る習慣をつけたいのであれば、さりげなく部屋の隅に置いておき、自分から入って探索をしたり、くつろぐように仕向けてあげるとよいでしょう。
猫が社会化を迎える生後2週から7週の間に楽しい体験をたくさんさせてあげると、大きくなってから周りの環境に馴染みやすい猫になるといわれています。
猫の注意をひくときや食事のときには猫の名前を呼んであげましょう。猫が飼い主のほうにやってきたら、ご褒美をあげたり、大好きなおもちゃなどで遊んであげましょう。名前が呼ばれたらいいことがあると覚えてくれます。
反対に大きな声や強い口調で呼ぶのは禁物です。もちろん叱るときに名前を呼ぶのはやめましょう。
【関連記事】
猫が噛む理由とは?効果的なしつけは?
猫の鳴き声。種類別の猫の感情としつけなど
【関連リンク】
噛み癖 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科
猫と暮らす上で気を付けたいポイント -夏と冬の季節編-
猫と一緒に暮らすにあたって、ほかにも飼い主として知っていたほうがいいポイントがあります。いくつか紹介します。
夏場の飼い方
猫の祖先はアフリカを出身とするリビア猫なので、犬よりは暑さに適した身体ですが、汗を分泌する汗腺が肉球と鼻先にしかないので熱の放出が難しいのは犬と同じです。猫にとって暑さに対する秘密兵器となるのが、得意のグルーミングです。猫は自分の唾液を皮膚にコーティングして蒸発させることによって熱も一緒に逃がし、体温を下げているのです。
上手に夏を過ごさせてあげるために
猫は快適な場所を見つける天才ですから、猫が自分で心地よい場所に移動できる環境を作ってあげましょう。暑さに強いといっても、留守番をさせるときなど、温度や湿度に注意をして、身体に熱がこもらないようにすることが必要です。
窓のカーテンを閉めて直射日光が入らないようにしたり、空調を使ったり、部屋の空気が循環するように工夫をして、猫の熱中症を防ぎましょう。
【関連リンク】
熱中症|みんなのどうぶつ病気大百科
冬場の飼い方
・寒さとカロリー要求量
私たちは食べることで体温を作り出しますが、寒い冬はとくに「食べること」が重要です。カロリーとは熱量をあらわす単位ですが、定義として1calは『1気圧で水1gを14.5度から15.5度まで1度上昇させるために要する熱量』といわれています。温暖な季節に比べると冬は身体も熱量を余計に作り出さなくてはいけません。
このため通常、寒い時期は、どうぶつのカロリー要求量は高くなります。もちろん、どうぶつ種、飼育環境や運動量により異なるので、どうぶつの状況に適した食事量になるよう調節してあげましょう。
ちなみに屋外で過ごす場合、厳寒期では温暖な時期の10%から20%増しのエネルギーを要求するといわれています。反対に、室内の温かい環境の中だけで過ごしているのに、外の寒さにあわせ、増量した食事を与えてしまうと冬太りにつながってしまいます。
【関連記事】
猫の体重はどれくらいが標準?何キロからが肥満?
・寒い時の体温調節
寒いときにブルブルッと思わず身体を震わせるのは、筋肉を振動させることにより熱を生産させ、体を暖めているのですが、ほかにも体温調節する生体機能として、次のようなものが挙げられます。
- 毛を立てたり膨らませたりして、身体の周りに空気の層を作って熱が逃げるのを抑える。
- 皮下脂肪は熱の放出を防ぐので、冬に備えて皮下脂肪を蓄える。
- 身体を丸めることで、外気に触れている表面積を減らして放熱を抑える。
猫がこんな仕草を見せたときは、寒いのかもしれません。日向ぼっこができるように部屋の動線を工夫してあげる、お気に入りの寝床に毛布を一枚余計に用意するなど、工夫をしてあげてくださいね。
・逃げられるようにする
お部屋を温めたり床面を温めたりする場合には、猫が熱いと感じたときに逃げられる場所を用意しましょう。低温やけどにも要注意です。また、こたつに潜りこんで出てこられなくなり体調を崩すこともありますので、こたつ布団の四隅の一つはテーブルの上にかけた状態にしたり、こまめにスイッチを入れたり切ったりすると安心です。
・ヤケドから守る
ストーブなどでやけどをすることも多いので注意が必要です。物理的に猫が近づけないように工夫をすると安心です。お出かけのときなど、暖房器具をつけたままにしておくのが心配なときには、タイマーをつけておいたり、湯たんぽ代わりとして、ペットボトルにお湯を入れて、しっかりとバスタオルなどでくるんでおくとよいでしょう。
・適度な湿度と換気
乾燥により呼吸器官を痛めてしまうことも多い時期です。乾燥している状態ではウイルス性疾患も伝播しやすくなります。暖房を効かせすぎてしまうとお部屋の中はカラカラになってしまいますから、湿度に留意したり、まめに部屋の喚気をするようにしてあげましょう。
【関連記事】
猫は寒がり!猫の暖房について知っておきたいこと。低温やけどにも注意!
猫と暮らす上で気を付けたいポイント -住環境編-
マンションでの飼い方
マンションで猫を飼うときに何より注意しなければならないのは、近隣住民へ迷惑をかけないことでしょう。たとえば、部屋の中に毛が落ちるからといって、ベランダでブラッシングするのはやめましょう。
また、猫は基本的に夜行性なので、夜中に元気よく駆け回ることがあります。下層階に住人がいる場合は、騒音にならないように工夫をすることが大事です。「脱走」にも注意が必要です。玄関に脱走防止のゲートを置いたり、ベランダのサッシを全開するときはケージに入れてあげるなど、外に出ないように飼い主が気をつけてあげるようにしましょう。
一人暮らしでの飼い方
一人暮らしの方が猫を飼う場合、仕事や通学のために猫だけで留守番をさせる機会が多いかもしれませんが、その際は猫が留守番中に事故に合わないよう、気をつけましょう。
猫は好奇心が強く、悪気はなくても危険な場所に近寄ったり、触れてはいけないものにイタズラをするかもしれません。猫だけを置いて家を空ける際は、近寄ってほしくない場所はドアを締めきったり柵を立てたり、誤飲や怪我につながりそうなものは出しっぱなしにせず猫の手の届かない場所にしまうなど、工夫してあげてください。
【関連記事】
一人暮らしで猫を飼うときの注意点、おすすめの種類は?
猫を飼って困ったこと

猫の飼い主にとっての困りごとといえば、「家具や壁で爪とぎをしてしまう」ことが真っ先にあげられるでしょう。ただ、個体差があるので、市販の爪とぎにしか興味を示さない子もいます。爪とぎについては、前述したので、ここでは省きます。
もうひとつの困りごとは、洋服に抜け毛がついてしまうことではないでしょうか。長毛種で、毛色が白色の猫の場合は、とくに目立ってしまいます。抜け毛対策としては、まめにブラッシングをしてあげることですが、それでも抜け毛がまったくなくなることはないので、「コロコロ」を常備して、飼い主自身がこまめに抜け毛を取るようにするのが一番の得策でしょう。
こんな時は病院へ
一緒に暮らしている猫の健康状態を見ることができるのは飼い主だけです。ブラッシングをしているとき、一緒に遊んでいるときなどに身体を触って、しこりがないか、痛がるところはないかなど、よく観察してあげましょう。
日頃からおしっこやうんちの状態を観察することも大切です。いつもと違って元気がない、食欲がない、おしっこやうんちの出がいつもと違うなど、「おかしいな」と思ったら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。早期発見・早期治療が肝心です。
病気になる前に…
病気は、いつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。

【関連記事】
子猫と暮らしたら知っておきたい!なりやすい病気の原因と治療法
子猫へのエサの与え方はどうする?適切な量は?
猫が噛む理由とは?効果的なしつけは?
猫の鳴き声。種類別の猫の感情としつけなど
猫は寒がり!猫の暖房について知っておきたいこと。低温やけどにも注意!
一人暮らしで猫を飼うときの注意点、おすすめの種類は?
【関連リンク】
ネコちゃんのトイレのしつけ|みんなのどうぶつ病気大百科
ネコちゃんを迎える準備|みんなのどうぶつ病気大百科
異物誤飲|みんなのどうぶつ病気大百科
ネコちゃんの爪のお手入れ|みんなのどうぶつ病気大百科
噛み癖 <猫>|みんなのどうぶつ病気大百科
可愛い子猫との出会いをお探しならハローべいびぃへ
末永く一緒に暮らせる、大切な家族と幸せな出会いをしたいものですね。そんな出会いをお探しなら、ハローべいびぃを活用してみては?全国のペットショップから探すことができる情報サイトです。エリアや品種などの条件から簡単に検索できるので、ぜひご覧ください!
アビシニアンの子猫を探す
アメリカン・カールの子猫を探す
アメリカン・ショートヘアの子猫を探す
エキゾチック・ショートヘアの子猫を探す
エジプシャン・マウの子猫を探す
オシキャットの子猫を探す
サイベリアンの子猫を探す
シャムの子猫を探す
シャルトリューの子猫を探す
シンガプーラの子猫を探す
スコティッシュ・フォールドの子猫を探す
スノーシューの子猫を探す
スフィンクスの子猫を探す
セルカーク・レックスの子猫を探す
ソマリの子猫を探す
トイガーの子猫を探す
トンキニーズの子猫を探す
ナポレオンの子猫を探す
ノルウェージャン・フォレスト・キャットの子猫を探す
ヒマラヤンの子猫を探す
ブリティッシュ・ショートヘアーの子猫を探す
ブリティッシュ・ロングヘアの子猫を探す
ペルシャ(チンチラ)の子猫を探す
ベンガルの子猫を探す
ボンベイの子猫を探す
マンチカンの子猫を探す
ミヌエットの子猫を探す
メイン・クーンの子猫を探す
ラガマフィンの子猫を探す
ラグドールの子猫を探す
ロシアンブルーの子猫を探す
ミックスの子猫を探す