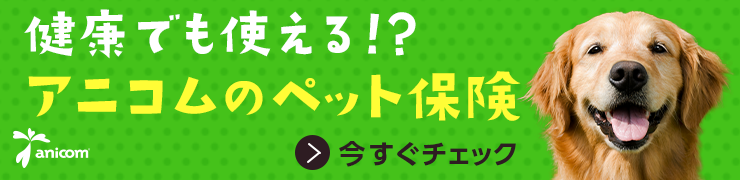飼い主さんなら誰もが、愛犬と末長くずっと一緒にいたいと思うものです。しかし人よりも犬の寿命が短いという事実は、残念ながら変えることができません。今回は、そんな犬の寿命について取り上げていきます。少しでも元気に長生きしてもらう方法なども合わせてご紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
犬の平均寿命は何歳?

「アニコム 家庭どうぶつ白書 2023」によると、2021年度の犬の平均寿命は14.2歳となっています。2008年度は13.3歳だったので、この13年ほどで0.9歳、年月に置き換えると10〜11ヶ月ほど延びたことになります。
犬の寿命のギネス記録は?
2023年2月、世界で最も長生きした犬として、30歳のポルトガルの犬「ボビ」(犬種:ラフェイロ・ド・アレンティジョ)がギネス記録に認定されたと発表されました。ボビは、同年5月に31歳の誕生日を迎え、記録を更新しています(2024年2月に認定取り消し)。それまでの記録は、1939年に29歳5ヶ月で亡くなった犬であったとされています。
31歳であれば、平均寿命の倍以上生きたことになります。「愛犬もこれくらい長く生きてくれたらいいなあ」といった、憧れや羨ましい気持ちを抱く飼い主さんも多いのではないでしょうか。
大型犬・中型犬・小型犬の平均寿命は?

犬種によって平均寿命にどれほどの差があるのか、具体的にご紹介していきます。なお、データは2021年度のものを参照しています。犬の平均年齢は人同様に年々延びている傾向にあるので、現在の数字とは異なる可能性があります。
大型犬
大型犬の中でも犬種によって身体や体質に違いがあるため、平均寿命が異なります。たとえばゴールデン・レトリーバーの平均寿命は10.7歳、ラブラドール・レトリーバーは12.7歳です。もう少し体重のあるバーニーズ・マウンテン・ドッグは、8.8歳となっています。犬全体の平均年齢である14.2歳と比較すると、短命な傾向にあることがわかります。
小型犬
小型犬も犬種によって12歳〜15歳と、3歳程度の差があります。大型犬同様、犬種が持つ特徴によってかかりやすい疾患などが異なるためです。たとえば小型犬の中でも特に長生きなのはトイ・プードルで、15.3歳ほどとなっています。一方でパグは12.8歳、ボストン・テリアは12.2歳と、短頭種は全体的に平均よりも寿命が少し短い印象です。
MIX犬の寿命は?
MIX犬は身体が丈夫で長生きしやすいといわれていますが、体重10キログラム未満は14.8歳、10〜20キログラムの犬も平均寿命は13.9歳という結果になっていて、平均寿命と同程度であることがわかります。
とくに小型犬は、MIX犬でなくても寿命がかなり延びてきているので、大きな違いは見られません。中型犬の場合も、柴犬の寿命は14.7歳で、MIX犬かどうかは寿命にそこまで大きな影響を与えないという見方ができそうです。
犬種別の平均寿命
アニコム『家庭どうぶつ白書 2023』によると、犬種別の平均寿命は以下の通りです。
| 犬種 | サイズ | 平均寿命 (歳) |
| トイ・プードル | 小型 | 15.3 |
| チワワ | 小型 | 13.9 |
| 混血犬(体重10kg未満) | 小型 | 14.8 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 小型 | 14.8 |
| 柴 | 中型 | 14.7 |
| ポメラニアン | 小型 | 13.8 |
| ミニチュア・シュナウザー | 小型 | 13.6 |
| ヨークシャー・テリア | 小型 | 14.0 |
| フレンチ・ブルドッグ | 中型 | 11.2 |
| シー・ズー | 小型 | 13.8 |
| マルチーズ | 小型 | 13.6 |
| カニーンヘン・ダックスフンド | 小型 | 15.0 |
| パピヨン | 小型 | 14.6 |
| ゴールデン・レトリーバー | 大型 | 10.7 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型 | 12.6 |
| ジャック・ラッセル・テリア | 小型 | 14.5 |
| ラブラドール・レトリーバー | 大型 | 12.7 |
| パグ | 小型 | 12.8 |
| キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型 | 12.3 |
| ミニチュア・ピンシャー | 小型 | 14.3 |
| 混血犬(体重10kg以上20kg未満) | 中型 | 13.9 |
| ペキニーズ | 小型 | 13.2 |
| イタリアン・グレーハウンド | 小型 | 14.6 |
| ビーグル | 中型 | 13.3 |
| ボーダー・コリー | 中型 | 12.9 |
| シェットランド・シープドッグ | 小型 | 12.5 |
| ボストン・テリア | 小型 | 12.2 |
| ビション・フリーゼ | 小型 | 14.6 |
| アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型 | 13.0 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 大型 | 8.8 |
| 日本スピッツ | 小型 | 13.9 |
| 秋田 | 大型 | 11.5 |
| スタンダード・プードル | 中型 | 12.4 |
| 混血犬(体重20kg以上30kg未満) | 大型 | 13.3 |
| シベリアンハスキー | 大型 | 11.4 |
| ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 中型 | 14.4 |
| 甲斐 | 中型 | 15.0 |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型 | 13.7 |
| ブルドッグ | 大型 | 8.8 |
| ノーフォーク・テリア | 小型 | 12.5 |
全体的に小型犬の方が長生きする傾向があり、40犬種の中で最も長生きなのはトイ・プードルの15.3歳となっています。
室内飼いと室外飼いで寿命は変わる?

室内飼育のほうが長生きする傾向にあります。近年、犬の寿命が延びたのは、室内飼育が増えたことなどによる飼育環境が大きな理由のひとつともいわれています。
室内飼育のほうが長生きするのは、さまざまなリスクを回避できるためです。屋外だと室内飼いに比べ、感染症や事故、熱中症などの危険性をはらみます。また、室内飼いの方が、そばにいる時間も長いので、飼い主さんが犬の異変にも早く気づくことができます。
長生きの秘訣は?

14歳という平均寿命の捉え方は人によると思いますが、多くの飼い主さんにとっては長いようであっという間、もっと一緒にいたいという気持ちにさせる数字なのではないでしょうか。とくにシニア犬になると、少しでも長く元気に生きてくれたらいいなと願う日々が続くことでしょう。何をしたら、もしくは何をしなければ寿命が延びるのか、考える時間も長くなると思います。こちらでは、一般的に長生きにつながるとされている犬への接し方の秘訣を取り上げます。
ただし、どんなに一生懸命愛情を注ぎながら正しい方法でお世話をしても、犬の体質などによっては、飼い主さんが思っていたよりも早くに亡くなってしまうこともあります。そこで最善を尽くせなかったことを後悔してしまう飼い主さんが少なくありませんが、寿命には犬が生まれつき持っている体力などが大きく影響してくることも、忘れないでください。
① 定期検診を受ける・異変があったらすぐに動物病院へ連れていく
予防接種以外にも、年に一回は定期検診を受けるようにしましょう。シニア犬の場合は、年に2回は診てもらうと安心です。普段生活している姿を見ているだけでは気がつかなかった疾患の早期発見ができるだけでなく、犬が病院に慣れるというメリットもあります。たとえ何の異常も見られない元気な犬であっても、万が一のときのためにかかりつけの病院をもっておきましょう。入院の際にも、犬にかかる精神的な負担が軽減されます。
また、近所にいくつか動物病院があるという場合には、それぞれ受診して比較するのもおすすめです。獣医さんと愛犬の相性や、診察の方針の違いなどを確認してみましょう。手術が得意な獣医さんや、メスを入れない治療方法を提案してくれる獣医さんといったそれぞれの特徴もあるので、愛犬に合う動物病院を見つけてあげてください。
②犬に合った食事を与える
犬にとって危険な食べ物はもちろん、人が食べるために味付けされたものは与えないでください。末期で犬用のフードは食べないなどの特別な事情でもない限り、犬がどんなに可愛い顔をしておねだりしてきても、与えないという選択をしてください。塩分や糖分の取りすぎにつながり、さまざまな疾患を引き起こす原因になります。一度味を覚えたり、もらえるものだと認識したりすると、毎回おねだりしてくるようになってしまいます。あげたくなってしまう気持ちは理解できますが、愛犬が病気で苦しまないためにも心を鬼にしましょう。
また、フードの選び方も重要です。粗悪なフードには添加物など犬の身体によくない原材料が使われていることが多いです。内臓や皮膚の疾患につながる可能性もあるので、できるだけ品質がよいものを選ぶようにしましょう。さらに、質の良いフードの中にも、愛犬がアレルギーを持っている原材料が使われていたり、体質によってうまく消化できずに便秘や嘔吐を引き起こしたりしてしまうものもあります。少量から試していき、愛犬の身体に合うかどうかを確認しながら理想的なフードを探していきましょう。
③適切な量の運動を
日々のお散歩をはじめ、家の中での遊びも含めた運動はとても重要です。ストレスの発散にもつながり、犬も満足感を覚えます。とくに体力がある犬の場合は、普通にお散歩したり遊んだりするだけではまだ足りないことがあるので、知育玩具などを取り入れながら遊ぶのもおすすめです。犬の認知症予防にもなり、心身の健康が保たれやすくなります。
一方で、シニア犬になると運動のさせすぎが逆に負担になってしまうこともあり、注意が必要です。また、ヘルニアなどを患ったことのある犬も、同様です。獣医さんに適切なお散歩の時間などを聞いて、多すぎず少なすぎない適切な量の運動をさせるようにしましょう。
④去勢・避妊手術をする
どうしても愛犬の子犬を見たいといった強い願望がない限りは、若いうちに去勢・避妊手術をしておくと愛犬の健康のためになります。男の子、女の子ともに生殖器官の疾患を引き起こすリスクを低くすることができるためです。多頭飼いの場合は、望まない妊娠を防ぐこともできます。また、発情期に見られる問題行動がなくなることで犬にとってもストレスが軽減されるほか、男の子の場合は本能から来る攻撃性のある行動を抑えることもできます。
ただし、去勢・避妊手術は思い立ったときにできるものではありません。適切な月齢や時期があるので、犬を家族に迎えた時点で獣医さんに相談しましょう。
犬たちとの限りある時間を楽しく幸せなものに

獣医療の発達や生活環境、飼育に関する正しい知識が広まったことなどにより、犬の平均寿命は延びています。WHO(世界保健機関)では「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」という健康寿命の定義がありますが、これは犬も同じです。少しでも長い健康寿命を目指して、犬たちとの限りある時間を楽しく幸せなものにしてくださいね。