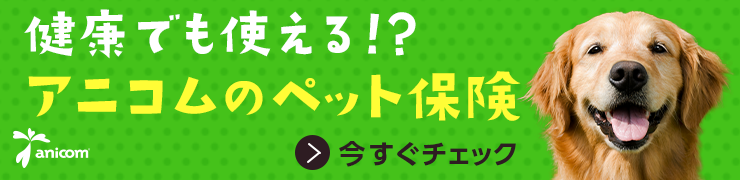愛犬の問題行動にお悩みを抱えている飼い主さまは少なくないですが、原因として考えられることのひとつに「犬の社会化」があります。家族として犬と一緒に日常生活を送るうえでとても大切なのが社会化です。今回は、そんな犬の社会化について解説します。
犬の社会化とは?

社会化とは、いろいろな音や場所、犬や人などに慣れさせて社会性を身につけることです。
犬は初めて見るものや音、知らない人と出会ったときには、強い恐怖と警戒心を抱くことがあります。警戒心から怯えたり、吠えたりといった行動を取ることがありますが、これが続くと、犬にも飼い主にもストレスになってしまいます。
恐怖心や警戒心が強く現れる前の子犬の時期に、トレーニングすることで、社会性を身につけることができます。ある程度大きくなってしまってから、社会性を身につけるのには時間と労力がかかります。これから犬を迎えるという方はもちろん、すでに愛犬と暮らしているという方もこれからでも遅くないので、役に立つ知識をつけておきましょう。
社会化の必要性

犬にもそれぞれ性格があり、それが個性となってその犬の魅力となりますが、アグレッシブな性格や引っ込み思案、お散歩嫌いなどは社会化不足が原因であるケースも考えられます。飼い主さまが一度「こういう性格だから」と諦めてしまうと、いつまでも改善されずに愛犬はもちろん、飼い主さまもストレスを感じ続けることになってしまいます。
犬の社会化は、想像以上に生活のさまざまなところに影響をもたらすものです。社交性などとは異なり、もっと生活の基盤となる要素を持っています。
社会化していないと…?
お散歩でほかの犬に対して強く威嚇をしたり異常に怖がったりするといった行動は、社会化不足に原因がある可能性が高いです。「社会化」という言葉の響きから、こういった行動を想像する方は多いのではないでしょうか。しかし、これ以外にもたくさんの影響があります。
犬はさまざまな音や匂い、刺激に敏感です。家の中にいても外の音などに反応する犬は多いですよね。極端に激しく反応する場合は、社会化ができていない可能性があります。
さらには、分離不安なども引き起こすことがあります。お留守番ができなかったりペットホテルや動物病院へ預けることが困難になったりと、犬だけでなくいざというときに飼い主さまも困るため、少しでも早く改善策を見つける必要があります。
社会化におすすめの時期

ほかの犬や知らない人と触れ合わせることだけが社会化トレー二ングというわけではないので、実際にはいつからでも可能です。それでも子犬の場合は犬種や個体差はあるものの大体生後3週から12、13週齢頃までに社会化期が訪れるので、この時期は逃さないようにしましょう。基本的にはすべてのワクチン接種が終わってからが理想的ではありますが、もし接種が終わっていなくても、社会化期を逃さないよう抱っこやケージなどのキャリーケースに入れて外へ連れて行くなどの工夫をしてみてください。家の中にはない環境に連れて行くだけで効果的です。
社会化させるポイントは? ポイント別に方法をご紹介
勘違いされがちですが、社会化は人見知りを直すことではありません。もちろんほかの犬と遊ばせることも大きなステップのひとつですが、ほかにもさまざまな方法があります。逆に、社会化できていない犬をいきなりドッグランなどへ連れて行くことは危険なので、ほかの方法を試してから少しずつハードルの高いことに挑戦するようにしてください。
人
まずは家族から。遊びを通じて「人と触れ合うのは楽しい」ということを認識させましょう。子犬であればすぐに慣れてくれることが多いでしょう。ただし、保護犬や成犬ですでに人に恐怖心を抱いている場合は少々ハードルが高いかもしれません。その場合は、人の性別で警戒心の抱き方が変わってくることなどもあるので、年齢や性別の異なる人が試してみてください。犬の性格に合わせて、焦らず少しずつがポイントです。ドッグトレーナーなど専門家に頼るのもひとつの方法です。専門家からのアドバイスは、愛犬はもちろん飼い主さまにも新しい発見があるかもしれません。
家族に慣れてきてから、ご近所さんやお友達とのふれあいにトライしてみましょう。
犬
他の犬に対して興奮しすぎたり、恐怖心を抱いたりしないように慣れさせておくことも重要です。犬同士の挨拶が落ち着いてできるよう練習するには、お互いにリードをつないだ状態で行いましょう。現在社会化トレー二ングをしていることを相手に伝えてから近づきましょう。自分よりも大きい犬は怖くても小型犬であれば問題なく触れ合える子や、同じくらいの大きさの犬だと上手に遊べる子などがいます。犬にも相性があるので、難しいと感じたら無理はさせないようにしてください。
万が一のときにすぐに犬同士を引き離せるように、リードは短めに持ちましょう。この際、伸縮できるタイプのリードは向いていません。
物や音
通常の暮らしを送っていれば避けることが難しい、車や自転車、チャイムなどの音。これらに敏感に反応してしまう習慣のまま放っておくと、愛犬は一日中休むことができないどころか大きなストレスを感じながら何年も過ごすことになってしまいます。また、車や自転車に反応してしまうとお散歩中に思わぬトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。車や自転車など動くものにも無関心でいることができたら、ご褒美を与えて、褒めてあげるようにしましょう。
音に対するトレーニングも同様です。救急車などのサイレン音も、反応せずにいることができたら、ご褒美を与えることを繰り返しましょう。その他にも、家の中の機械音なども慣れさせておくとよいでしょう。掃除機や電子レンジ、ドライヤーの音などいろいろな生活音を聞かせて、慣らしていくようにしましょう。
いずれも根気のいるものではありますが、犬の一生のあり方まで大きく変わってくる大切なトレーニングです。早めにしっかり身につけさせましょう。
愛犬との生活をよりハッピーなものにするために

犬の社会性は、単なるコミュニケーション能力とは異なります。そのため、あまりに社会性がないとペットホテルへの宿泊を拒否されてしまうなど、一緒に暮らしていくうえで大変になってしまうかもしれません。犬が感じるストレスについては取り上げましたが、もちろん一緒に暮らす家族にも影響が出てきます。愛犬との生活をよりハッピーなものにするためにも、しっかり犬の社会化に取り組んでくださいね。
【関連記事】