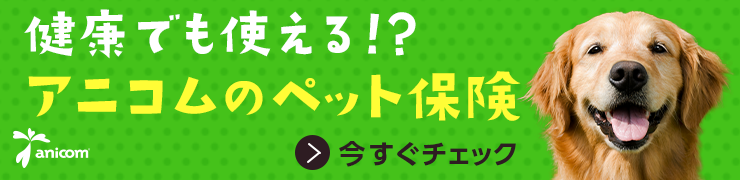犬は豊かな感情を持つ生き物です。日常で感じるさまざまな気持ちを、仕草や鳴き声など全身で表現しています。人間にとっての言葉のようなもので、ひとつひとつに意味があります。今回は鳴き声に焦点を当てて、種類や理由、必要となるしつけや対処法を解説していきます。
犬が鳴くのには理由があるの?

犬が意味もなく鳴くということはありません。何かを訴えたいときか、自分や家族の身を守ろうとしているとき、もしくは溢れ出る感情を鳴き声で表現しています。まれに、反響する自分の鳴き声を聞くのが楽しくて吠える犬がいますが、これにも楽しむという目的がありますよね。
そして、鳴き方にはバリエーションがあります。理由ごとに鳴き方が異なるので、それぞれの鳴き声がどのような意味を持つのか、見ていきましょう。
「ワンワン!」と鳴く
犬の鳴き声といえば「ワンワン」を連想する人がほとんどだと思います。犬によってトーンや声の太さは大きく異なりますが、一般的に身体のサイズが大きくなるほど声は低くなります。小型犬の鳴き声は大型犬よりも高いので、同じ「ワンワン」でも「キャンキャン」のように聞こえることが多いです。
警戒している
家の中から外に向かって「ワンワン」と鳴いたり、散歩中に出会う犬に向かって鳴く場合は、相手に対する警戒心の表れであることが多いです。怖がりな子や縄張り意識の強い子はこのシチュエーションでよく鳴く傾向にありますが、相手の存在に慣れたり、恐怖心を取り除くトレーニングをすることで鳴かなくなります。
よく鳴く犬とあまり鳴かない犬がいますが、もっとも大きな違いがみられるのはこの警戒吠えです。犬種による違いだけでなく、個体差や育て方によって大きく異なるともいわれています。
興奮している
興奮したときに鳴く犬の心理には、喜びや要求などさまざまなものがあります。アジリティーなどの競技に出場する犬が鳴きながら競技に参加している姿やドッグランで鳴きながら走る姿をよく見かけますが、これは典型的な興奮吠えです。
興奮吠えは必ずしも悪いことではありませんが、興奮がエスカレートするとパニックや思わぬ事故を引き起こす可能性もあります。興奮がエスカレートする前に犬の感情を落ち着かせられるようにしつけましょう。
要求している
ごはんの時間の前や、おやつをもらう前、飼い主の食事中、おもちゃで遊んでほしいときなどに見られます。控えめに「ワンッ!」と鳴くタイプもあれば、激しくワンワン鳴いてしまうタイプもありさまざまです。
要求吠えに応えてしまうと、「吠えればしてもらえる!」と学習させてしまい、鳴き方がエスカレートしてしまうかもしれません。愛犬が鳴いているときは心を鬼にして無視を貫き、鳴き止んだら一緒に遊んだりごはんをあげるようにするといいでしょう。
「ウーッ!」と唸っている
わかりやすい感情表現です。近寄りがたい鳴き方ですよね。ときには歯茎を見せたりと、多くの場合表情も連動しています。
威嚇している
相手を下に見て自分の優位性を示そうとするときや、相手に対して不快感を表すときに見られます。明らかにネガティブな表現なので、放置しておくとけんかやトラブルの原因になりかねない問題行動なので、ふさわしい方法で対処しましょう。
独占欲
犬は縄張り意識やモノに対する独占欲が強く、これを阻害されそうになると唸ることがあります。とくに生命に直結する食べ物に関しては、取られそうになると強い抵抗を覚えます。これは自然なことですが、拾い食いなどで口にしたものを放させたいときには、きちんと出せるようにしつけておかなければ、万が一のときに危険です。
「オフ」や「放せ」などのコマンドを教えるのは根気が必要ですが、愛犬を守るためにもしっかりしつけておきましょう。
「クーン」と高い声で鳴く
「クーン」や「クンクン」といったか弱い鳴き方の中にも、いくつか種類があります。鳴き声は似ていても、尻尾や耳、目の表情から細かい感情を判断することができます。
さみしい・不安
飼い主が出かける前などにクンクン鳴くのは、さみしさや不安が原因であることが多いです。この項目に限り「鳴く」ではなく「泣く」と表現してもいいかもしれません。尻尾は下がり、目にはさみしげな表情を浮かべます。
犬が飼い主と離れるタイミングでさみしいと感じるのは自然なことですが、あまり過剰にさみしがるのは分離不安である可能性があります。さらに飼い主がいなくなっても鳴き続けてしまうのは、近隣からの苦情につながりかねません。分離不安を引き起こす背景にはさまざまなことが考えられるので、もしその可能性が考えられる場合は、原因を見極めて適切な対応を施しましょう。
おねだり
飼い主が食べているものをほしがるときや甘えたいときに出す声で、目は上目遣いになり、尻尾は上がっていることが多いです。可愛い表情でおねだりしてくるので、何かを食べているときには思わず与えてしまいそうになります。しかし、人間の食べ物を与える習慣をつけてしまうと、食事のたびにお互いに大変な思いをすることになってしまうので、基本的には与えないようにしましょう。
「ワオーン」と遠吠え
オオカミのトレードマークとしても知られる遠吠えは、本能による行動です。大きく遠くまで響く声なので、遠吠えをする犬と暮らす人の中には悩んでいる人もいるかもしれません。
オオカミが遠吠えをする理由は群れの仲間に合図を送るためとされていますが、現代の日本に暮らす犬が遠吠えをする理由はこれ以外にもいくつか考えられます。
コミュニケーション
家族とのコミュニケーションの一つとして用いる、平和的な鳴き方です。外出中の遠くにいる飼い主を想って遠吠えをする犬もいます。
テリトリーの主張
近隣の犬が、遠吠えをしたり鳴き声を聞いたりしたあとに続けて遠吠えをした場合は、テリトリーの主張であることが多いです。縄張り意識が強い犬によくみられます。
苦痛がある
不快なことがあるときや飼い主が出かけることをさみしがる際に見られる遠吠えは、精神的な苦痛を表現していることが多いです。先ほども触れた分離不安はさまざまな問題行動の引き金となるので、それが遠吠えとして現れる可能性もあります。
音に反応
サイレンなど特定の音に対して遠吠えをするなら、その音を不快に感じているか、面白がっていることが考えられます。尻尾が垂れていたら前者である可能性が高いですが、尻尾を振って喜んでいる様子であれば、後者かもしれません。
「キャンッ!」
小型犬の「ワンワン」が「キャンキャン」に聞こえる場合もあるという話題に触れましたが、この項で取り上げる「キャンッ!」は、短く一回放つ声です。
痛いとき
何かに対して痛みを覚えたときに「キャンッ!」と鳴くことがあります。痛くなくても驚いたときに鳴く犬もいますが、とくに心当たりのないタイミングでこの鳴き方をしたら、一度全身に傷などがないかみてください。とくにお散歩中などは、何かを踏んで肉球や爪に傷がついてしまっていることも考えられます。
犬の鳴き声がうるさいとき。対策やしつけについて

犬の鳴き声が過剰な場合は、近隣トラブルにつながりかねません。飼い主が知識を身につけ、できるだけ早く対処しましょう。飼い主との信頼関係がしっかりと築けていなかったり、適切なしつけができていなかったりと、その原因は犬ではなく飼い主にあることがほとんどです。犬種や遺伝のせいにはせずに、その犬にあったしつけを飼い主がすることが大切です。
とはいえ、犬の鳴き声はコミュニケーションのひとつです。しつけができていて正常な回数・ボリュームの鳴き声で鳴くことはあります。それが気になる場合には、窓やカーテンを防音仕様にするなどの工夫を施してみてください。また、窓を開っぱなしにしないといった少しの工夫で愛犬の鳴き声対策をすることができます。
まとめ

犬の鳴き声からはさまざまな犬の感情を読み取ることができます。言葉を使って話すことができないからこそ、声色やトーンに耳を傾けることで、愛犬の気持ちを少しでも理解してあげたいですね。
【関連記事】
【みんなどうやって解決してる?】要求吠え対策3つのワザ|anicom you