犬では循環器、特に心臓に関連した病気がいくつかあります。その中の一つに「心筋症」と呼ばれる病気があります。心筋症とはそもそもどんな病気で、症状はどんなものがあるか、そして治療方法や予防対策などについてご紹介します。
まずは犬の心筋症について知ろう

心筋症という病気は、「心機能障害を伴う心筋の疾患」と定義されています。心臓はそのすべてが筋肉で構成されていて、絶えずバランスよく収縮と拡張を繰り返しながら、全身に血液を送り込むポンプとしての働き(全身に血液を送り出す機能)をしています。この筋肉の機能が何らかの形で障害されてしまうことで、心臓のポンプ機能がうまく働かず、全身の血液の循環が滞ってしまう状態である「心不全」を発生させるものが「心筋症」といわれます。
現在、獣医療でみられる心筋症は、拡張型心筋症、拡大型心筋症、拘束型心筋症、不整脈源性右室心筋症に分類されます。そのうち、犬では拡張型心筋症が最も多く、散発的に拡大型心筋症や不整脈源性右室心筋症が確認されることがあります。
拡張型心筋症
拡張型心筋症は犬の心筋症の中で最も多くみられるタイプです。特定の犬種あるいは特定の家系で発症する傾向があるため、遺伝性の病気の可能性が考えられています。そのほか、栄養の欠乏や薬物による誘発、代謝異常などによって心筋の活動性が低下したことが原因として挙げられることがあります。心臓から肺あるいは全身に血液を送り出す心室の空間が異常に拡張してしまい、本来、心室の筋肉が持ち合わせている収縮機能が不十分となり、心臓から血液を押し出すことができず、心臓内、さらには体全体に血液がたまってしまうことになります。その結果、全身に「うっ血」と呼ばれる血液の流れがよどんでしまう状態を引き起こします。胸部のレントゲン写真では心臓の拡大が確認され、エコー検査では右心室と左心室の内腔(心室の空間)が拡大していることが確認できます。この拡張型心筋症は6~8歳の成犬で多く発生する傾向があります。
拡大型心筋症
拡大型心筋症になると、心筋(心臓を構成する筋肉)が分厚くなるので、血液を送り出すための心室のスペースが狭まってしまいます。そして、心室内に十分な血液を貯められないことによって循環がうまくできなくなります。失神や呼吸困難、突然死などを起こすことがありますが、多くの場合、無症状であるといわれています。前述した拡張型心筋症では、心臓の拡大がみられますが、拡大型心筋症では心臓の大きさに大きな変化はみられません。一方で、同時に不整脈が発生することもあります。なお、拡大型心筋症は犬で発生することは稀であるといわれています。
拘束型心筋症
拘束型心筋症の特徴は、心筋が収縮する機能についてはおおよそ正常であるものの、心室が十分に拡張できないことによって、心室に十分な血液が入り込まず、その結果、全身に送りだせる血液量が制限を受けてしまうことです。犬よりも、猫で比較的発生する確率が高い心筋症です。ちなみに、猫ではすべての心筋症のうちおよそ20%程度を占めるといわれていますが、犬ではかなり稀です。
不整脈源性右室心筋症
不整脈源性右室心筋症は、肺に血液を送り出す右心室にある心筋が、脂肪組織に置き換わることで収縮や拡張といった機能が損なわれるタイプの心筋症です。これによって心不全のほか不整脈を発生させる可能性があるのが特徴です。特に心室の収縮が異常に増加する心室頻拍と呼ばれる状態に至りやすく、これにより突然死を生じることがあります。拡張型心筋症と比べると発生頻度はまれで、このタイプも遺伝性疾患の可能性があると考えられています。
心筋症にかかりやすい犬種は?

心筋症は他の心疾患と比べると、犬種によって発症しやすさが異なります。もちろん該当した犬種が必ず心筋症を発症するというわけではありませんが、以下でご紹介した犬種と生活している場合は、定期的に動物病院で心臓のチェックをうけるとよいかもしれません。
(1)拡張型心筋
ドーベルマン、グレート・デン、ボクサー、セント・バーナードなどの大型、超大型犬種に多く見られますが、スパニエル種でも発症しやすいことが知られています。
(2)拡大型心筋症
ポインター種は肥大型心筋症を生じやすい犬種であるといわれます。このほか、ジャーマン・シェパードやドーベルマン、アメリカン・コッカースパニエルでも発生例があります。
(3)不整脈源性右室心筋症
そもそも、不整脈源性右室心筋症自体が心筋症の中でも珍しい部類に入りますが、ボクサーで多く、その他ラブラドール・レトリバーやシベリアン・ハスキーなどで発症した報告があります。
犬の心筋症の症状

心筋症で共通してみられる症状に、うっ血性心不全と呼ばれる状態があります。うっ血とは血液の流れが必要なところに行き渡らず滞ってしまう状態を指します。また、ご紹介した通り心筋症にはいくつかのタイプが存在していて、それぞれのタイプごとに症状にも違いがありますが、ここでは心筋症によって生じる症状にはどのようなものがあるかをご紹介します。
咳・呼吸にまつわる症状
心筋症をはじめ、うっ血性心不全の状態になると呼吸器に症状が表れることがあります。心筋症によって心筋、特に左心室に何らかの変化が発生すると、左心室にある僧帽弁という弁がきちんと機能しなくなります。これにより、本来左心房から左心室に一方通行で流れるべき血液が逆流してしまいます。さらにこれがきっかけとなって左心房に血液を届けている肺静脈の血液に滞りが出ることで、肺水腫(※)に至る可能性が高くなります。
※肺胞内に液体成分が貯留することで、酸素と二酸化炭素のガス交換ができなくなり、全身の低酸素状態や呼吸困難を引き起こす疾患のこと
食欲不振
軽度の心筋症の場合は、日常生活で特に異変を感じないこともありますが、進行とともに食欲に変化が現れることがあります。一般に食欲が減退しているような場合は、後述の運動不耐や呼吸不全といった問題も合併していることが多くみられます。
運動不耐性
ちょっと動いただけですぐ息が上がってしまう、お散歩に行きたがらない、あるいは室内であっても動きたがらない…。このような状態を運動不耐性といいます。心臓は、体を動かす際に酸素を含んだ血液を全身に送り込まなければなりません。しかしながら、うっ血性心不全によってこの血液の運搬十分機能しない場合は血液中の酸素不足が原因で、皮膚が青っぽく変色する「チアノーゼ」や、短時間で疲れてしまう様子が見られます。また、必要とされる血液を送らなければいけない状態なので、心臓自身は心拍数を上げようとしますが、うまく血液を送れない状態にさらに拍車をかけるため、犬にとっては余計につらい状態になってしまいます。
血栓
拡大型心筋症では、左心室から左心房に向けて血液の逆流が生じ、この影響で左心房に血栓が形成されることがあります。この血栓が部分的にちぎれ、、それらが血流にのって、末端の血管で詰まってしまうことがあります。
突然死
心筋症では心筋の構造や機能に大きな異常が生じます。心筋の内部には、規則正しい収縮を行うための刺激電動路という電気の通り道がありますが、心筋症になると、心筋の構造や機能に大きな異常が生じます。その結果、不整脈が発生します。この不整脈は、軽度であれば心臓の機能を著しく障害しませんが、致命的な不整脈が発生すると心停止し、最悪の場合突然死につながることもあります。
犬の心筋症の治療法
犬の心筋症では、心筋そのものの問題で十分に血液を送れなくなる結果、心拍数が高くなる傾向があります。心拍数が高くなりすぎると、心臓自体の疲労を招くほか1回の収縮で血液を送る「1回拍出量」が減少し、血液運搬の効率が悪くなります。そのため、心拍数をセーブするお薬を使うことがあります。またその他にも、不整脈が発生した場合には、それに合わせた抗不整脈薬を併用します。心臓自体が疲労し、機能を大きく損なうことがないような治療をお薬で行います。
また、心筋症によって生じたうっ血性心不全では、肺水腫をはじめとした呼吸にも影響が及ぶ症状が見られることがあります。肺水腫を起こしている状態では、利尿剤を用いることがあるほか、血流をスムーズに行き届かせるため血圧の調整を行います。負担のかかっている心臓にこれ以上の負担をかけないようにすることが目的です。
治療費は?どれくらい通院が必要?
『みんなのどうぶつ病気大百科』によると、犬の心筋症における1回あたりの治療費は11,491円程度、年間通院回数は5回程度です。
病気はいつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。
「JARVISどうぶつ医療センター Tokyo(公式サイト)」はこちら
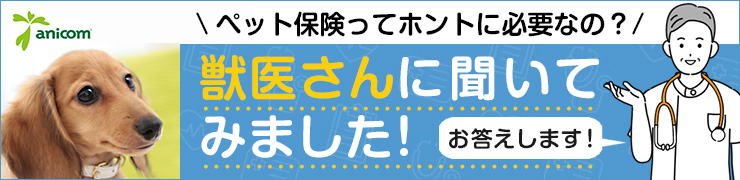
犬の心筋症の予防法
残念ながら、犬の心筋症に対する有効な予防法はありません。犬種特有の性質が大きく影響していることがあり、生活の中で気を付けられることが確立されていないのが現状です。そのため、心筋症を疑う症状がみられた場合は、早めに獣医師の診察を受けること、また心筋症になりやすいといわれる犬種の場合は、定期健診をして異常がないかをチェックすることが非常に重要です。
心筋症について正しく理解を

犬の心筋症は心臓疾患全体で考えると、それほど多く発生するものではなく、また比較的発生しやすい犬種が明らかになっています。発生しやすいとされている犬種と生活されている場合は、普段の様子をよく観察し、疑わしい様子や症状があれば早めに獣医師の診察を受けましょう。
心筋症を発症した場合、それによる呼吸困難や食欲不振といった生活に支障が出る状態を軽減していく必要があります。残念ながら、心筋症は根治できる病気ではありません。しかし、心筋症について正しく理解し、適切に接することで過剰な負担をかけずに過ごすことができます。日頃の生活で何か異変を感じる部分があれば、かかりつけの獣医師に相談しましょう。













