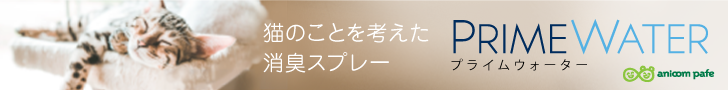みなさんの中には「耳掃除」が大好き、という方が多いかもしれません。毎日綿棒で掃除しないと気がすまない、という方だっていることでしょう。
しかし、猫に耳掃除をしてあげるとなると勝手が違うもの。多くの猫は嫌がるものです。では、猫に嫌がられずに耳掃除をする方法はあるのでしょうか。ここでは、耳掃除の正しいやり方、嫌がるときの対処法などをご紹介したいと思います。また、猫の耳の状態で気持ちを読み解く方法もあわせてご紹介します。
猫の耳ってとっても重要!
猫にとって、音をききとり、まわりのかすかな動きをキャッチする耳はとっても重要な部位。猫といえば、ネズミを追い掛け回すイメージがありますが、まさにそのために猫の耳は大きく進化し、発達しました。外に敵がいないか、獲物がないかなどの情報を猫は耳を使って察知しています。耳から正確に情報を得るために、猫は12種類以上の筋肉を使って、耳を動かしているというから、驚きです。
人間が聞くことができる波長は最大でも20キロヘルツ。それに対して猫は60キロヘルツの音を聞くことができます。もちろん高齢になるにつれて聞ける音の範囲は異なってきますが、猫にとって耳がどれほど大切かわかります。
耳掃除はしたほうがよいのか。
しっかりと直立している耳を持つ猫の場合は、耳の中の通気を保つことができるためムレにくく、それほど汚れが溜まりやすいわけではありません。そのため、汚れてもいないのに、無理をして頻繁に耳掃除をする必要はありませんし、逆に耳掃除をしすぎることで、耳を傷つけてしまうことに気を付けるべきです。
一方、スコティッシュフォールドのような「折れ耳」の猫の場合、通気性が悪いため、耳の中で雑菌が繁殖しやすくなります。汚れがたまりすぎない程度に耳掃除をしてあげることをお勧めします。
【関連記事】
スコティッシュ・フォールドってどんな猫?性格や特徴は?
猫の耳に黒い汚れがあるとき
猫の耳垢の多くは、黒い汚れとして出てきます。耳のしわの溝に少しつくくらいであればあまり気にする必要はありませんが、その量が異常に多かったり、強い痒みや匂いを伴う場合には、放置すべきではありません。耳ダニの寄生や、マラセチア(酵母菌)の感染や外耳炎が疑われます。かかりつけの獣医師に相談してみてください。
【関連リンク】
耳疥癬|みんなのどうぶつ病気大百科
外耳炎|みんなのどうぶつ病気大百科
猫の耳掃除の必要性
本来、猫の耳にはきちんと自浄能力があり、耳の中の古い角質や分泌物は外側に排除されるようになっています。健康な猫であれば、耳掃除は「気になったときだけ」すればよいのです。
家で耳掃除をするときの注意点
日常ケアとして、おうちで猫の耳掃除をするときは、まずもってご自身の爪に注意してください。伸びていたり、尖っていたり、欠けていたりすると、簡単に耳を傷つけてしまいます。
また、初めての場合や、まだ慣れていない場合、猫は全力で耳掃除を嫌がるものだと心得ておきましょう。シャンプーのときと同じで、急に始めたり、必要以上に押さえつけたりすべきではありません。
たとえば、耳洗浄液(イヤークリーナー)を、いきなり耳に入れようとすると、激しく驚いてしまいます。慣れるまでは、次に紹介する方法で、優しく、少し手間をかけて掃除してあげましょうね。
耳掃除の方法
では、いよいよ実践編です。猫が不安がらないようにするためにも、まずは飼い主さんがリラックスしましょう。
耳掃除といっても、掃除の方法はいろいろ。猫によって嫌がってしまう可能性もありますのではじめはゆっくりと優しく、猫に合った方法で挑戦していきましょう。
コットンやガーゼで拭く方法
おうちでのケアと言う意味での猫の耳掃除で、最もポピュラーで安全な方法は「コットンやガーゼで拭き取る」方法です。目に見える範囲だけで構わないので、優しくふき取ってあげましょう。猫の耳の中の皮膚は大変薄いので、力を入れてこすり取るのではなく、撫でるように。もし、こびりついた汚れがあっても、無理して取ろうとせず、コットンを湿らすなどして、丁寧に優しく拭ってあげてください。
①猫が落ち着く体制を整える。
②頭から耳にかけてをゆっくり撫でてあげる。
③湿らせたガーゼやコットンで、耳の見える範囲だけを優しくふき取る。
洗浄液はどんなものがおすすめ?
猫の耳掃除アイテムのひとつとして、耳洗浄液(イヤークリーナー)があります。これは、耳垢がたまっていてコットンやガーゼでは取れない場合などに役立ちます。
耳に直接洗浄液を垂らすことも可能ですが、慣れていない猫の場合は嫌がります。そんな場合は、コットンに洗浄液を含ませて耳の中に指を差し込み、届く範囲をぬぐってあげるようにしましょう。もちろん、指を強く押入れたりしないように!
耳のお手入れに慣れてきたら、直接、耳の中に数滴ほど洗浄液を垂らしてしばらく待ち、耳の付け根あたりを外から軽く揉んでやると(強く押さえてはいけません。鼓膜を破ってしまうこともあります)、内部の汚れが浮いて出てきます。その汚れをコットンでふき取ってしまえば耳掃除はおしまいです。
中に入れた洗浄液が多少残っていても、掃除後に猫が首を振ったりすると残りの液が耳から出てきます。そうでなくても、乾燥してなくなってしまうので心配ありません。市販のものもたくさんありますが、どれを選べばいいか迷う場合は、かかりつけの動物病院で購入すると良いでしょう。
オリーブオイルは使ってもよい?
あなたの周りにいる先輩飼い主さんたちの中には、「猫の耳掃除にオリーブオイルを使っている」という方がいらっしゃるかもしれません。確かに、web上でも活用しているという声を見かけます。ただ、洗浄液と同じように耳の中にオイルを垂らすようなことはNGです。
目に見える範囲をコットンやガーゼでぬぐう際、すべりをよくするために利用する程度なら問題ありません。
綿棒を使うのはアリ?
綿棒で自身の耳掃除をこまめにしている人は、猫にも同じように綿棒を使ってしまうかもしれません。しかし、綿棒は、かえって汚れを奥に押し込んでしまったり、耳の内部の皮膚を傷つける恐れがあります。猫の耳掃除に綿棒は使うべきではない、というのが定説です。
イヤークリーナーはおすすめか?
耳の中の皮膚は薄く傷つきやすいので、ガンコな耳垢を指先などでかき出すことはケガの原因になりかねません。そうした意味で、耳掃除用のイヤークリーナーは、耳垢や古い皮脂を浮かせてくれるため、優れていると言えるでしょう。
ただ、もともと猫の耳の中に傷があったり、デキモノがある場合などは、イヤークリーナーが原因で思わぬトラブルを招く恐れもあります。耳の状態が良くない場合は控えるか、イヤークリーナーを使って耳掃除をしても問題ないか獣医師に相談してみましょう。
耳掃除の頻度は?
耳掃除の頻度は、猫種(耳のカタチ)や耳垢のできやすさによっても違います。愛猫の耳のコンディションを確かめながら、行なってください。
嫌がるときの対処法
耳に液状のものを入れられるのは、本能的に嫌なものです。これは、猫だろうが人間だろうが、変わらないはず。しかし、頻度はどうあれ耳掃除をする機会は訪れます。猫に過度なストレスを与えないようにするためには、嫌がらないようにすることと、嫌がったときにその記憶が後々まで残らないように対処することが重要です。
まず、嫌がられないようにするには、猫がリラックスしている時に飼い主さんが優しく(しかも素早く!)掃除してあげることが成功のコツです。むやみに刺激したり、緊張状態の時に行なうとなかなか上手に掃除できないだけでなく、耳の中に傷を付けてしまう恐れもあるので注意しましょう。
嫌がった時には、サッと手を引くことも大事です。ムリに押さえ込んだり、耳を掴んだりするとケガの元。今後、怖がって耳掃除をさせてくれなくなることすら考えられます。嫌がる場合は「今回は諦めて、次の機会を狙おう」と考えてあげましょうね。
猫の耳垢にはどんな特徴がある?

ここまで、あまり良くない状態の耳垢について紹介しましたが、正常な状態がどんなものかもお伝えしておきましょう。人間の場合は、ドライタイプとウェットタイプがある耳垢ですが、猫の場合は…? 詳しく見ていきましょう。
どんな色?どんな形状?
猫の耳は、人間と違いL字型の構造になっています。そのため、耳の奥までにホコリなどの異物が入らないよう、分泌物を使って固めるようになっています。この固まったものが、耳垢となります。
茶色っぽく少しべたついた感じがする場合は正常と考えて問題ありません。ただ、住んでいる環境や個体差によって、出方が異なります。まったく出なかったり、期間限定でしか出ない場合、逆にコンスタントに出る猫もいます。その子にとっての「普段の量、出方」をまずは飼い主さんが把握することが重要です。
病気の兆候はわかる?
猫は一般的に、耳垢がたくさん出てくることはまれです。なので、耳掃除が必要だと思うほど耳垢が目立つのは、何らかの病気や不調のサインかもしれないので、注意が必要です。
猫にとって耳は平衡感覚を取るための大事な器官です。耳の様子が普段と違う、または、耳垢が出てきている、耳から変なニオイがする、ということに早めに気付いてあげられるようにしておきましょう。
放置しすぎると耳ダニ(耳疥癬)に?
耳垢が出てきていたり、耳から臭いがするときには、外耳炎や耳ダニになっている可能性があります。外耳炎になると、大量の耳垢や臭いのする分泌物が出てきます。特に湿度の高い時期などは、外耳炎が発症しやすくなりますので、定期的に耳の様子をチェックしてあげましょう。少し汚れていたら耳の掃除をして清潔にしてあげ、あまりにもひどい場合には病院へ行きましょう。
耳ダニも症状は同じですが、原因は外耳道の表面にミミヒゼンダニが寄生することです。家の外などで、ダニが寄生している猫と接触することで感染します。特に子猫は発症しやすく、外に出る機会が多い猫にも発症しやすい病気です。
どちらも予防するには、毎日欠かさず耳の様子をチェックすること。見るだけではなく臭いもチェックすることで、万が一の変化に気づいてあげることができるでしょう。
【関連リンク】
耳疥癬|みんなのどうぶつ病気大百科
猫の耳の形で感情や気持ちがわかる?
いざ猫の耳の掃除をしよう!と思っても、猫の気分によっては掃除のタイミングが違うことも。猫の耳が表現する気持ちや感情を読み取って、耳掃除=怖くない ということを理解させてあげましょう。
①耳をピンっとたてている
音や動きに敏感に反応している状態です。集中していたり、じーっと獲物を見つめるときに耳がピンとたつことがあります。
①耳を後ろに倒している
耳を後ろに倒しているときには2つパターンがあります。1つは、初めて見るものや初めて匂いを嗅ぐものに対して、ちょっと様子を伺いながら近づいているとき。例えば、自宅に嗅いだことのない匂いがする人が入ってきたり、新しいおもちゃやクッションなどがあるときにこうなります。2つ目は、人の近くに来て耳を後ろに倒しているとき。これは「撫でて~かまって~」という甘えん坊のサイン。手のひらの下に頭を潜り込ませて、アピールをします
②耳をピクピクとしている
耳をピンとたてている状態よりも、より動きがあるものや音がたくさん聞こえているときに耳が動きます。神経質になってまわりの様子をうかがっている場合がありますので、突然ふれたり、大きな音をたてたりするのは控えましょう。
③耳が横に倒れている
猫の耳が横に倒れているときは要注意!「近づかないで!」のサインです。こんな風になっているときは、猫に近づかずそっとしておくのが一番。無理に撫でたり、近づこうとすると攻撃してくる可能性もあります。
毎日チェック、定期的に掃除。で病気を予防。
猫にとって、とっても大切な“耳”。わが子に健康で、元気に過ごしてもらうために毎日欠かさずチェックして、病気を予防したいですね。コミュニケーションの一環として掃除をしてあげらるようになると、猫にとっても飼い主にとっても嬉しいことですね。
病気は、いつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、病気になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。
【関連記事】
スコティッシュ・フォールドってどんな猫?性格や特徴は?
猫の外耳炎の治療法や予防法について