インコ・文鳥などの鳥類にペット保険は必要?かかりやすいケガ・病気について

犬のように散歩の必要がなく、飼育の手間があまりかからないインコ・オウムなどの鳥類。犬猫ほど飼育費用がかからないですし、名前を呼ぶとやってきてくれたり、甘えてきたりするなど、人気の高いペットです。
しかし、鳥類にも当然ケガや病気など健康上のリスクがあります。ここでは、インコ・オウムなどの鳥類はどのような病気にかかりやすく、どれくらいの診療費が必要なのか、また鳥類もペット保険に入るべきなのかを解説します。
インコ・文鳥などの鳥類が加入できるペット保険とは
ペットがケガや病気をした場合は動物病院へ連れていくことになります。その際、人と同じように窓口で診療費を支払いますが、ペットには公的な保険がないため飼い主が全額負担しなければなりません。この高額な診療費を補償するのがペット保険です。
ペット保険といえば犬や猫の保険を想像する方が多いかもしれませんが、犬や猫だけでなく鳥類が加入できる保険もあります。しかし、犬や猫が入れるプランに比べ、その数は決して多くはないのが実状です。
インコ・文鳥などの鳥類はペット保険に加入すべき?
インコをはじめとする鳥類の診療費は体が小さい分、犬や猫ほどはかからないものの、レントゲン検査や超音波検査、血液検査などが重なったり、入院や手術が必要になった場合には、高額になる可能性もあります。鳥類は病気を隠す習性があるとも言われますので、病気を発見した時にはすでに高度な医療を施さなければいけない状態になっていた、ということもあり得るでしょう。
普段からの健康観察を心がけると同時に、不測の状況に備えてペット保険に加入し、安心して動物病院に連れていける環境を作っておくことがおすすめです。
インコ・文鳥などの鳥類に年間どのくらい診療費がかかっている?

そもそも、インコ・オウムなどの鳥類には年間どのくらいの診療費がかかるのでしょうか。
アニコム損保の「家庭どうぶつ白書2019」の「鳥の年齢別の年間診療費(1羽あたり)」によると、0歳~2歳までは年間で10,000円を切る診療費となっていますが、年をとるにつれて平均診療費が増加しており、0歳と5歳では約5倍近くの差があります。
こうした調査から、他のペットと同じように鳥類も高齢になるほど診療費がかかる傾向が見られます。なお、鳥類のペットとして人気のあるセキセイインコの寿命は約10年ほどと言われています。
※1 参照:アニコム家庭どうぶつ白書2019
インコ・文鳥などの鳥類がかかりやすいケガ・病気
インコ・オウムなどの鳥類は呼吸器や消化器、生殖器の疾患にかかりやすいと言われていますが、具体的にどのようなケガや病気が多いのでしょうか。
胃炎
インコがなりやすい「胃炎」。ごはんを食べない、羽を膨らませている、元気がないなどの症状がみられます。その他には、強い嘔吐症状が見られます。インコはごはんを食べないとすぐに状態が悪化してしまいます。
インコは羽がある分、痩せたことに気づきにくいため、ごはんを食べる量や排泄物の量など些細な変化を見逃さないようにしましょう。
毛引き症(自咬症)
鳥類は羽を綺麗に保つために毛づくろいします。くちばしで触っているだけなら問題はありませんが、羽を引き抜いたり噛みちぎったりするなどの過剰な行動が見られる場合は「毛引き症」にかかっている可能性があります。また、皮膚や肉をかじってしまう症状は「自咬症」と呼ばれます。毛引き症から自咬症に進行することもあれば、自咬症を急に発症することもあります。
原因としては、環境の変化や運動不足などによるストレス、退屈や寂しさなどが考えられますが、インコなどの鳥類が感染するウイルスの1つ「ボルナウイルス」やダニ、シラミなどが原因で発症する場合もあります。また遺伝的素因も無視できず、これらのさまざまな要因が絡み合って発症するとも考えられています。
関連記事:
鳥の自咬症ってどんな病気?
卵詰まり
「卵詰まり」は卵が卵管に詰まってしまう状態をいいます。産卵日近くや産卵中に羽を膨らましてうずくまるなどの状態が見られた場合は注意しなければなりません。
卵詰まりは、体調不良や日光不足、発育不良や運動不足、肥満など、いくつかの原因が重なって発症することが多い症状です。保温やカルシウム剤の投与、ビタミン剤の投与などを施し、自力出産を促します。効果が見られなければ手術で卵を取り出すことになります。
各種感染症
鳥類の感染症として代表的なものに、オウム病(クラミジア症)があります。原因菌はクラミジアと呼ばれ、オウムに限らずあらゆる鳥類、または人にも感染します。体温低下や食欲不振、結膜炎などの症状が見られ、抗生物質を用いた治療が必要です。
これらの症状の他、胃に感染し嘔吐や下痢などの症状が現れるAGY(メガバクテリア症)、羽毛障害やくちばしの形成異常、免疫不全を起こすオウム類嘴(くちばし)羽毛病(PBFD)などの病気を発症する場合もあります。
インコ・文鳥などの鳥類が健康に過ごすためには?

ペットに健康に長生きしてもらうためには、過ごしやすい飼育環境を整えることが欠かせません。では、鳥類の場合にはどのような点に気をつければよいのでしょうか。
デリケートな体の体温管理
インコ・オウムなどの鳥類は体温が高く、寒さが苦手な動物です。また、急な温度変化も苦手です。夏場は冷房が直接当たらない場所にケージを置くなどの配慮が必要となります。冬場は、地域や環境によっては室内でも保温器具を設置したほうがいいでしょう。
ただし、温めすぎて高体温症にならないようにも注意が必要です。保温器具で温めつつ涼しい場所も用意するなど、体温調節できる環境を用意してあげましょう。
インコ・文鳥などの鳥類にとっての有害物質に注意
人間の生活において身近なものが鳥類の体調に悪影響を及ぼすこともあります。食べ物では、チョコレートやアルコール類、玉ねぎやネギ、ニラ、アボカドなどがあげられます。また、ポトスやアロエ、ポインセチアといった観葉植物には毒素が含まれているので、放鳥をした際にインコ・オウムなどの鳥類がついばむことのないよう注意しなければいけません。誤って食べると、嘔吐、下痢、呼吸困難などの中毒症状を引き起こし、最悪の場合は死に至るケースもあります。同様に亜鉛や鉛にも要注意です。カーテンウェイトや雑貨の塗料に含まれている場合があります。
運動不足を解消させる
運動不足が病気の原因となる場合もありますので、時々放鳥をして運動をさせてあげることが大切です。必ず窓が開いていないことを確認し、1日1時間程度ケージから出してあげましょう。有害なものを摂取しないよう気をつけ、他にペットがいるなら放鳥の間は他のペットはケージに入れておきます。
フォージングができる環境を用意する
私たちは狭いスペースにずっと閉じ込められているとストレスを感じたり身体を動かしたくなったりしますが、それは鳥類も同じです。ケージの中で身体を動かさないままでいるとストレスを感じてしまいます。
野生の鳥類は起きている間は餌を探してあちこちを飛び回っています。この行動をフォージング(採餌行動)と呼びます。フォージング中の鳥は運動と思考を繰り返している状態であり、体は健康に保たれていますが、ペットは餌を与えられるため生き延びるためのフォージングが必要ありません。そのぶん、退屈に感じる時間が長くなってしまうのです。野生動物のようにフォージングができる環境を用意し、ストレスを軽減してあげるようにしましょう。
フォージングができる環境を整えるには、ペットショップなどで販売されているフォージングトイを使うのがおすすめです。中に餌が入っているのは見えるけれど簡単には取り出せないようになっているおもちゃで、何か工夫をすれば餌が食べられることを学ぶことで退屈が解消され、ストレス軽減につながります。
また、フォージングトイで遊ばせる際は声をかけるなどのスキンシップをとり、寂しさを和らげてあげることができます。
フォージングの注意点
なかなか興味を示してくれない場合には、好きなおやつを使ったり、食餌を与える前のお腹がすいている時間に試しましょう。それでも難しい場合、毎日体重測定や食事量を管理して体型をみていきましょう。お腹いっぱいでいつでも食べられる状態では、餌探しをしてくれません。
ペット保険に入る際の注意点とは
インコ・オウムなどの鳥類がペット保険に入る際にはいくつかの注意点があります。
まず、保険プランの対象動物であるかどうかをチェックしましょう。犬や猫を対象とした保険プランは多く存在しますが、鳥類が加入できる保険はまだ少ないです。
また、保険会社によって補償内容は大きく異なりますので、通院・入院・手術補償の限度額および限度日数や補償内容の確認も忘れずにしなければいけません。さらに、新規で加入できる年齢や継続できる年齢も商品によって異なります。
アニコムの「どうぶつ健保 ふぁみりぃ」なら、犬・猫だけでなく鳥も入ることができます。
3歳11ヶ月まで新規加入が可能ですので、詳しくはこちらをご覧ください。
ペット保険で万が一の時の備えを
ここまで、ペット保険の観点から、インコなど鳥類のケガや病気のこと、予防法を解説しました。
鳥類は種類や性格にもよりますが、愛情を持って育てればコミュニケーションを取ることもでき、飼い主になついてくれます。大切な家族として長く健康に過ごしてもらいたいですよね。また、万が一の時には迷いなく病院に連れて行くことができるよう、ペット保険に加入してケガや病気にしっかり備えておきましょう。

記事作成:アニコム損害保険株式会社
ペット保険シェアNo.1のペット保険専門の損害保険会社で、グループ創業は2000年。動物病院の窓口で使用できる便利な「どうぶつ健康保険証」や、「どうぶつ健活(腸内フローラ測定)」などのサービスを提供しています。『涙』を減らし、『笑顔』を生みだす保険会社を目指して、グループをあげてケガや病気の予防促進に取り組んでいます。
※シェアは各社の契約件数から算出しています。
㈱富士経済発行「2025年ペット関連市場マーケティング総覧」調査
関連記事
アニコム損保が取り扱っている保険商品についてご案内いたします。
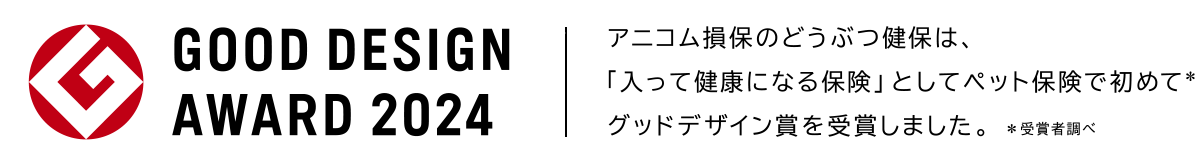

ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!


