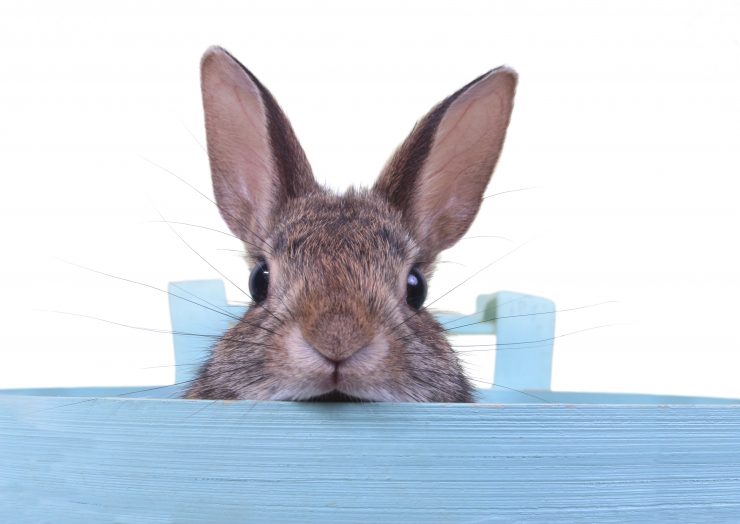うさぎのチャームポイントといえば長い耳。感情に合わせて動く姿はかわいいですよね。
耳は聴覚や平衡感覚を担っている器官ですが、病気になった場合にはどのような症状が見られるのでしょうか。今回はうさぎの耳の病気についてわかりやすくお伝えしていきます。
知っておきたいうさぎの耳の構造
耳は、外耳、中耳、内耳の3つに分類されます。
うさぎの長い耳の部分を耳介といい、そこから耳道、鼓膜までを「外耳」といいます。
うさぎの耳介は大きいため、音を集める能力に優れているだけでなく、血管が豊富で体温を調節する働きもあります。大きな耳に、たくさんの血管が通っていることで、うさぎは耳で体温調整を行うことができるのです。
鼓膜の奥を「中耳」といいます。中耳腔、耳小骨(じしょうこつ)、耳管からなります。
中耳のさらに奥を「内耳」といいます。蝸牛(かぎゅう)、前庭、三半規管からなります。
耳介で集められた音は耳道を通って鼓膜を振動させ、それが耳小骨、蝸牛と伝わり、聴神経を刺激して脳に音として認識されます。また、三半規管は平衡感覚を保つのに大切な働きをする器官です。
外耳炎
うさぎの外耳炎ってどんな病気?原因は?

外耳に炎症が起こる病気を外耳炎と言います。細菌、真菌、耳ダニなどの感染によって起こります。伸びすぎた爪で耳を傷つけることで発症することもあります。
また、ロップイヤー種は耳が垂れていることから、蒸れて菌が増えやすいため注意が必要です。
うさぎの外耳炎はどんな症状が出る?
耳垢がたくさん出るようになります。細菌感染の場合には白色、耳ダニの場合には茶褐色の耳垢になることが多いです。
耳や頭を振る、後ろ足でひっかく、耳を傾ける、耳を痛がる、臭うなどの症状が見られることもあります。特に耳ダニの場合には非常に強いかゆみが認められます。
うさぎの外耳炎はどんな治療をするの?
耳垢を顕微鏡で観察することで原因を特定します。
治療は、イヤークリーナーで耳垢を取り除き、原因に応じて抗生剤、抗真菌剤、駆虫薬を投与します。
うさぎの外耳炎の予防法は?

爪の伸びすぎは、耳を傷つけてしまう原因になるため、定期的に爪切りをしましょう。
不衛生な環境や、気温や湿気が高い環境では菌が増えやすくなります。排泄物はこまめに掃除し、部屋の空気の入れ替えもこまめに行って、環境を清潔に保つようにし、適切な温度、湿度管理を行いましょう。
ロップイヤー種は外耳炎になりやすいため、耳をこまめにチェックするといいでしょう。
家で耳そうじをする場合には、イヤークリーナーで湿らせたコットンで優しく拭ってあげる程度にしましょう。綿棒やコットンで強くこすると傷つけてしまうため注意が必要です。自分で行うのが心配な場合には、動物病院やうさぎ専門店でみてもらうのがおすすめです。
中耳炎
うさぎの中耳炎ってどんな病気?原因は?
中耳に炎症が起こる病気を中耳炎といいます。
細菌感染、特にパスツレラ菌が原因になることが多いです。その他には、ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌などが原因になることもあります。
外耳炎から中耳に炎症が波及したり、鼻炎から耳管を通じて中耳に炎症が広がったりすることで中耳炎を起こします。 また、中耳炎から外耳炎や内耳炎に移行することもあります。
うさぎの中耳炎はどんな症状が出る?
中耳炎のみのときには、症状が見られないケースが多いです。
外耳炎がある場合には耳や頭を振る、耳を傾ける、耳垢が出るなどの症状が認められます。内耳炎があると、首を傾げる、転がる、立てないなどの症状が見られます。
うさぎの中耳炎はどんな治療をするの?
耳鏡(耳の奥を見る機械)で耳道や鼓膜を観察します。また、レントゲン検査で中耳に内容物がないかを調べます。耳垢を採取し、菌の種類や効く抗生剤を調べる検査をします。

その結果に応じて、必要な抗生剤を投与します。鼓膜を切開し、中を洗浄する処置を行うこともあります。
うさぎの中耳炎の予防法は?
外耳炎や鼻炎から中耳炎になることがあるため、耳垢が多い、くしゃみをするなどの症状がある場合には早めに病院に相談するようにしましょう。パスツレラ菌は、生活環境の変化や不衛生な環境、ストレスなどによって増殖しやすいため、適切な環境に整えてあげるようにしましょう。
内耳炎
うさぎの内耳炎ってどんな病気?原因は?
内耳に炎症が起こる病気を内耳炎と言います。中耳炎と同様に、パスツレラ菌の感染が原因になることが多く、その他には、ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌などが原因になることもあります。
外耳炎や鼻炎から中耳炎になり、そこから内耳炎に波及するケースが多いです。また、歯の伸びすきによる歯根膿瘍[しこんのうよう](歯の根元が膿む病気)から内耳炎になることもあります。 内耳は脳に近いため、脳炎や髄膜炎に進行する可能性があり注意が必要です。
うさぎの内耳炎はどんな症状が出る?
内耳にある三半規管は平衡感覚を保つ働きがあるため、内耳炎になると首を傾げる(斜頚)、立てない、転がる(ローリングといいます)、眼球がゆれる(眼振)といった症状が見られます。立てないことにより、上手にごはんが食べられなくなります。
うさぎの内耳炎はどんな治療をするの?
中耳炎と同様に、耳鏡検査、菌の検査、レントゲンなどを行います。その結果に応じて抗生剤の投与や、鼓膜切開、洗浄を行います。ごはんが食べられない場合には、食事の介助が必要になります。また、体が転がってしまうことで体や眼を傷つけないように、クッションなどで保護してあげましょう。
うさぎの内耳炎の予防法は?

外耳炎や鼻炎、歯根膿瘍から内耳炎になることが多いため、気になる症状があれば早めに病院に連れていくようにしましょう。また、生活環境の変化や不衛生な環境、ストレスの多い環境では菌が増殖しやすいため、飼育環境を適切に整えてあげるようにしましょう。

まとめ
うさぎの耳が病気になると、さまざまな症状が見られるようになります。特に、内耳炎まで進行してしまうと、食事がうまく取れなくなることで弱ってしまい命に関わることもあるため注意が必要です。そうなる前に、気になる症状があれば早めに病院を受診し、飼育環境にも気を配るようにしましょう。