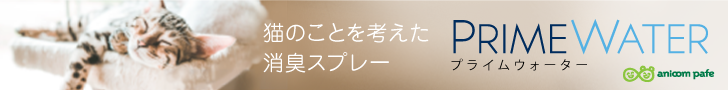あまり直視したくない現実ですが、家の中にはダニが無数に存在します。ダニは環境が整うと爆発的に繁殖し、人間にとってはアレルギー症状を引き起こす原因になり得ます。もちろん、猫にとってもダニは大敵です。
飼い主さんと猫の健やかな毎日を守るためにもダニ対策は必須! ここでは、少し勇気を持ってダニと向き合ってみることにしましょう。
猫に寄生するダニの種類

ダニは、湿度60%以上(より“最適”なのは、60~80%)で、温度が25~28度、酸素があって、カビやフケ、アカやダニの死骸、食べかすなどがあればどこででも繁殖してしまいます。ジメジメした梅雨の時季は特に気になりますね。上記のような条件が整わなくとも、ある程度までなら生き延びることもできるのだとか…。
そう聞くと背筋がゾッとしてしまいますが、実は湿度が下がると生存率も低くなっていくそうです。このことを踏まえながら、まずは、猫の被毛や皮膚に寄生してしまうダニの代表例をみてみましょう。
マダニ
マダニは、世界中で800以上の種類が知られていて、日本には47種類が生息しているとされています。
■形状:成虫は体長が3~8mmで、肉眼で見ることができます。吸血し、飽血(満腹状態)になると、なんと10~20mmもの大きさになります。
■生息域:春から秋にかけて活動が活発になりますが、温暖な地域では冬でも活動しています。日本全国の自然環境が豊かな場所のほか、市街地周辺でも確認されています。
■寄生方法:吸血するために地上1m位の植物の葉陰で野生動物や人を待ち伏せし、その体に付着します。そして、比較的やわらかい部位の皮膚に咬み付いて、セメント物質を分泌して固着します。その後、麻酔様物質の含まれた唾液を分泌して吸血します。セメント物質で固着したマダニは除去しづらくなり、皮膚科での処置が必要となる場合があります。
参考:国立感染症研究所HP
東京都健康安全センター「マダニにご注意!~マダニQ&A~」
【関連リンク】
マダニ媒介性感染症について知ろう! <猫>|どうぶつ病気大百科
ヒゼンダニ
ヒゼンダニは、「皮膚疥癬症(ひふかいせんしょう)」という激しいかゆみや皮膚炎を起こす皮膚病の原因として警戒が必要なダニです。
■形状:雌の成虫の場合、体長約400μm・体幅約325μm。卵形、円盤状で、肉眼ではほとんど見えません。雄は雌よりさらに小型です。
■特徴:卵→幼虫→若虫→成虫と、約2週間で成熟します。
■寄生方法:幼虫、若虫、雄成虫は皮膚の表面を歩き回るため、 皮膚同士の接触によって簡単にうつってしまいます。また、皮膚内に掘った穴や毛包内に隠れていたりするため、ダニの寄生部位を特定するのは難しいと言われています。多頭飼育をしている場合、1頭に寄生するとあっという間に広がってしまったり、寄生された猫を抱っこすることで、一時的に飼い主さんにもうつる恐れがあります。
参考:国立感染症研究所、どうぶつ親子手帳
ミミヒゼンダニ
主に耳たぶから鼓膜までの間(外耳道)の表面に寄生し、「耳疥癬(みみかいせん、通称:耳ダニ症)」を引き起こします。耳垢が特徴的で、黒褐色でボロボロと崩れやすく、“コーヒーの出がらし”に例えられることがあります。こちらも非常に寄生しやすく、ダニが寄生している猫との接触によってうつったり、外の環境に出る機会がある猫が家の中に持ち込むこともあるようです。
ツメダニ
いくつか種類がありますが、代表的な「フトツメダニ」は体長が0.3mm~1.0mm。梅雨時や秋口になると増殖するとされています。マダニやヒゼンダニなどのように人間や動物に対して吸血はせず、他のダニを捕食するとされます。しかし、まれに間違って(!)人間を刺して体液を吸うこともあるそうです。そうした場合、咬まれてから1~2日後に赤く腫れて、かゆみが出て来る場合があります。
猫にとって警戒したいのは「ネコツメダニ」。
これは、0.4mm~0.5mmぐらいの大きさで、頭に巨大なかぎ爪を持っているのが特徴です。寄生した動物の皮膚で卵を産み、増えていきます。「ツメダニ症」という皮膚疾患を引き起こし、軽度のかゆみと大量のフケを発生させます。また、人間がこのダニに刺されると、発疹を起こし、強いかゆみや痛みを伴うとされています(ダニ刺咬性皮膚炎)。
ダニはどうやって寄生する?
次に、最も重要な「ダニはどうやって猫に寄生するのか」について見ていきましょう。想像すると鳥肌モノではありますが、可愛いわが子のため。それぞれの注意点が分かれば、きっと猫をダニから守ることもできるはずですよ!
屋外で寄生する
ダニは自然界にも存在します。生息場所は、木々や草花、動物などさまざま。そのため、自由に外に出られる猫の場合、散歩の途中でダニが寄生してしまうことがあります。外に出ることがないよう、しっかりと気をつけてあげましょう。
家の中で寄生する
家屋内に無数に生息するダニが、猫に寄生することがあります。後述しますが、一緒に暮らしている他の動物に寄生していると、そこからダニがうつることも。
家の中では、とくに湿度が高く、ダニのエサになりやすいものが溜まりがちな場所にはダニが繁殖しやすいので注意が必要です。こまめに掃除するだけでなく、風通しをよくして湿度が高くならないようにコントロールするようにしましょう。
猫の寝床を定期的に日干ししたり、乾燥機などでしっかりと乾燥させることも効果的です。
「ダニ対策を!」と、薬剤などを利用するケースも考えられますが、猫の健康を害する恐れがあるので、利用する場合は、噴霧・塗布した薬剤が猫の口に入ることがないよう、徹底した後処理を心がけましょう。
犬に寄生したダニが寄生する
犬も一緒に暮らしている場合、散歩の途中で一緒に連れてきてしまうケースが考えられます。犬の散歩をやめてしまうことは現実的ではないので、犬のダニ対策を並行して行うようにしましょう。
とくにマダニは草むらなどに多く潜んでいるので、散歩ルートがこのような場所だった場合はルート変更を考えましょう。
また、散歩の後は、目の縁や鼻の周り、耳、足の指の間、背中などを中心に異変がないか念入りにチェックしてあげましょう。定期的にマダニの駆除薬を投与することも効果的なので、心配なことがあればかかりつけ医に相談するのもオススメです。
人が持ち込んだダニが寄生する
外から家の中にダニを持ち込む犯人が飼い主さんやその家族、ということも大いに考えられます。この場合、自然の中に存在するダニだけでなく、職場や学校、施設など屋内に生息するダニも考えられそうです。
定期的にダニを駆除し、しっかりと始末するようにして、増やさない努力を欠かさないようにしましょう。
ダニの寄生によって猫が感染症を発症した場合の症状
さまざまな対策を行ったとしても、効果が果たせずにダニが寄生してしまうケースもあるでしょう。そうした際には猫にどんなことが起こり得るのか、代表的な症状を挙げてみたいと思います。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」です。2013年以降は渡航歴のない方が国内で発症した例が確認されていて、人間、犬、猫の区別なく感染するおそれがあります。
マダニは成長するために、哺乳類の血液を吸います。このマダニがSFTSウイルスを保有していると、吸血の際にウイルスが感染し、発症に至ります。原因不明の発熱や嘔吐、下痢などの消化器症状、倦怠感などの症状が認められるのですが、今のところ治療法は対症療法しかなく、有効な薬剤やワクチンはないとされます。致死率も60~70%と非常に怖い病気です。
ライム症
マダニが媒介となってボレリアという細菌の一種が引き起こす「ライム症」。筋肉痛や関節痛、頭痛、発熱、悪寒や全身倦怠感といった、インフルエンザのときのような症状を伴うことがあります。病原体が全身に拡散するに伴い皮膚症状、神経症状、心疾患、眼症状、関節炎、筋肉炎などの症状もみられるようになります。
日本国内ではまだワクチンが使用できないため、マダニが活発に活動する時期にむやみに藪に立ち入ったりしないよう、注意が必要です。
猫ヘモプラズマ感染症
病原体が猫の赤血球に感染し、それを破壊することで貧血を引き起こします。ダニやノミによる媒介、咬傷などによって感染すると考えられています。
元気がなくなったり、発熱したり、食欲不振や脱水症状のほか、貧血による粘膜の蒼白、脾臓が大きくなる(おなかが大きくなったように見える)などの症状が見られます。
予防薬やワクチンは開発されていないため、まずは原因になりそうなことから身を守ることが重要です。なお、「猫ヘモプラズマ感染症」は「猫伝染性貧血」と呼ばれることもあります。
【関連リンク】
ヘモプラズマ感染症|どうぶつ病気大百科
ダニが猫に寄生しないようにするには

ここまで読み進めると、ダニの恐怖を感じざるを得ないのですが、ダニが寄生しないために日頃から対策を講じることはできます。いくつか例を挙げてみたいと思います。
ノミ、ダニの寄生を予防をする
ノミ、ダニの寄生予防には、定期的に予防薬を投与する方法があります。予防薬には、猫の身体に薬剤を垂らして投与するスポットオンタイプや錠剤タイプ、スプレータイプなどがあります。どのタイプがよいか、獣医師に相談してみるとよいでしょう。
ブラッシングをする
ダニの中には体内に入り込んでしまうものもいるため、ブラッシングで完全に除去することは難しいものです。しかし、マダニのように比較的大きなサイズのものは、被毛の中に潜り込んでしまう前であれば、ある程度の除去は期待できるでしょう。
家で一緒に暮らす猫はさておき、外で散歩してきた猫や犬がいる場合は、散歩のあと、家に入る前にしっかりとブラッシングしてあげるといいですね。
シャンプーに気をつける
猫は自分で全身をなめて毛づくろいをするため、シャンプーをあまり必要としませんが、シャンプーを行う際には「マダニが食いついていないか」注意深く見ながら行いましょう。見つけた場合、絶対にしてはならないのが「手で潰すこと」です。もし黒っぽいまたは茶色っぽい小さな粒を見かけたら、無理に引っ張ったりせずにかかりつけ医に診てもらいましょう。
潰すと、食いついている部分がそのまま食い込み皮膚炎をおこすことなどが考えられます。マダニを見つけても、絶対に手で潰さないようにしましょう。
また、「ダニが気になるから」という理由で毎日シャンプーをする、といった行為は皮脂を落としすぎて逆に皮膚炎を誘発させてしまうおそれがあるので注意しましょう。
もしスポットオンタイプの薬剤で対処する場合は、薬剤が皮脂とともに放出されることで効果が発揮されるため、使用予定日前後のシャンプーは避けるのが望ましい場合があるようです。薬剤を処方してもらう際にかかりつけ医に確認しましょう。
【関連記事】
猫にシャンプーは必要!?|必要な場合の仕方やコツをご紹介
まとめ
ダニの恐ろしさは、一度徹底した対策を行ったとしても、その効果がいつまでも続くわけではない、という点だと言えます。そのため、まず猫を迎える際にはしっかりとしたダニ対策を。
そして、迎えたあとには定期的に除去薬を処方してもらったり、こまめに掃除を行ったり、日頃から湿度のコントロールをしておくことが欠かせません。
また、とくにダニの活動が活発になるとされる初夏から秋頃には普段以上に注意したいものです。
病気になる前に…
感染症は、いつわが子の身にふりかかるかわかりません。万が一、感染症になってしまっても、納得のいく治療をしてあげるために、ペット保険への加入を検討してみるのもよいかもしれません。
【関連リンク】
マダニ媒介性感染症について知ろう!|どうぶつ病気大百科