ご家庭の冷蔵庫に常備されている卵。人間にとっては完全栄養食とも呼ばれるほど栄養価が高く身近な食材ですが、猫にとってはどうでしょうか?健康上、問題にならなければ与えてみたいという飼い主さんもいらっしゃるかもしれません。
今回は、猫が卵を食べても問題ないのか?食べさせる場合のメリット・デメリットや、与える場合の注意点についてお話しします。
猫に卵をあげるのは正しい?
猫は元来、肉食動物です。野生の猫は蛙、ねずみ、鳥、虫などを補食して生活しています。たとえば、母鳥を捕食すると、その身体の中にある卵も一緒に摂取することになります。このため、猫は自然界でも卵を摂取する機会があることから、卵を食べることは間違いではないと思われます。しかし、実際与える際には猫にとってメリットとなる点もありますが、与え方によってはデメリットとなる点もあります。
メリットは?
猫が必要とする食事中の栄養素は、主にタンパク質です。卵には豊富な動物性タンパク質が含まれていて、猫に必要な必須アミノ酸も摂取できるため、猫の筋肉の成長を維持したり、皮膚、毛質を良くしてくれます。また、脂質も多く含まれ、猫が食事として摂取する必要がある必須脂肪酸(リノール酸、αリノレン酸、アラキドン酸、EPA、DHA)も摂取することができます。
デメリットは?
卵には、猫に必要な栄養がそろっている反面、生卵のまま与える場合、病原菌(サルモネラ菌や大腸菌)の感染リスクを考えなければなりません。日本では生のまま食べる習慣があるので、海外に比べると卵に対する汚染予防の管理が徹底されていますが、それでも注意が必要です。猫が病原菌に感染してしまうと、下痢・嘔吐・発熱といった症状が出る可能性があります。
また、卵白に含まれる「アビジン」という酵素は、生卵の状態で与えると、猫の健康に悪影響を与えることが知られています。
知っておきたい卵と猫の話

猫に生の卵白を与え続けると、「ビオチン」というビタミンが欠乏し、猫の健康を害することがあります。この原因になるのが上述した卵白に含まれる「アビジン」という酵素です。
「ビオチン」はビタミンB群の水溶性ビタミンであり、猫にとっては被毛のつやの維持や、皮膚の健康維持にとても重要なビタミンです。また、神経系の機能維持にも重要とされます。猫は「ビオチン」を食事からしか摂取できないため、ビオチン欠乏症になると皮膚や毛質が悪くなり、脱毛やフケ・皮膚の乾燥などが起こってきます。
卵白に含まれる「アビジン」は、この「ビオチン」と結合しやすい特性があります。生卵のまま卵白を与え続けると、食事で摂取した「ビオチン」が「アビジン」と結合してしまい、体に吸収されずに排泄されてしまいます。
猫に卵をあげるときの注意点
猫に卵を与えるときは、なるべく生ではなく加熱して与えることをおすすめします。病原菌の代表であるサルモネラ菌や大腸菌は加熱により死滅します。卵白に含まれる「アビジン」も熱で失活するため、加熱すると安心です。
また、初めて猫に卵を与える場合は、卵に対する食物アレルギー反応を考慮して、少量ずつから与えることをおすすめします。アレルギー症状がでた場合、皮膚の痒み、嘔吐や下痢の症状もみられることがあります。与えた後はしばらくの時間、猫の様子を観察してあげましょう。
加熱した卵、特に卵黄は勢いよく食べてしまうと、喉に詰まらせてしまう危険性があります。無理のない量で細かく砕いて与えると良いでしょう。
【関連記事】
猫の下痢は何で起こる? 飼い主が知っておきたい原因と対策
卵に含まれている栄養素
卵は栄養豊富であり、卵1個(60g)あたりのエネルギーは90kcalで、Lサイズの卵になると100kcalほどの栄養価があります。その内、卵白は17kcal、卵黄は70kcalほどで卵黄のほうがカロリー豊富です。また、3大栄養素としては、タンパク質7.3g、脂質6.1g、炭水化物0.1g、この他に卵にはビタミン、カリウムやカルシウム、鉄といったミネラルも豊富にふくまれています。
肉食である猫にとっては、十分なタンパクと脂肪を摂取できる食べ物といえるでしょう。
卵をあげるときの調理法
卵を加熱して与える場合、卵白が透明な状態から白くなるまで加熱するとアビジンが失活し、ビオチン欠乏を気にせず与えることができます。ただし、加熱の前に卵白と卵黄を混ぜてしまうとアビジンとビオチンが結合してしまうので、卵焼きやオムレツ、スクランブルエッグにするよりは、卵白と卵黄を混ぜずに調理する目玉焼きやゆで卵のほうがおすすめです。
また、油や調味料は脂質や塩分、糖分が多く含まれるため、取りすぎると心臓や腎臓に負担がかかる可能性があります。ヒトにとっては少量でも、猫にとっては過剰になる場合もあるので、油や調味料は使用しないで調理しましょう。
卵をあげすぎてはいけない理由
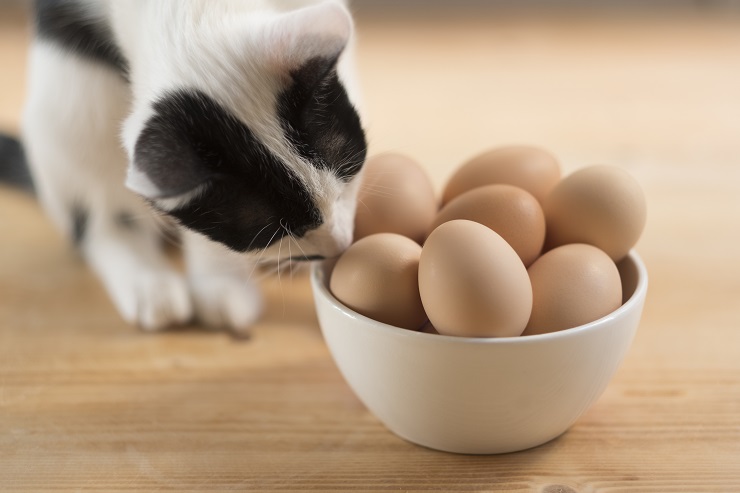
卵は栄養素から考えると、効率よくエネルギーを摂れる食材ですが、卵1個分でも90kcal前後と高カロリーなため、猫に与えすぎるとカロリーの摂りすぎから肥満につながり、猫の健康を害することになってしまうかもしれません。
あげすぎるとどうなる?
卵を与え過ぎると、摂取したエネルギーを消費しきれずに、脂肪として体内に蓄えるようになります。脂肪は内臓、特に肝臓などの臓器に広がっていったり、血管に沈着したりすることで、体に悪影響を及ぼします。また、肥満による体重増加で関節炎を引き起こしたり、他にも糖尿病、尿路疾患や心臓疾患を患うリスクが上がってしまいます。
【関連記事】
猫の体重はどれくらいが標準?何キロからが肥満?
あくまでもあげすぎないことが大切
健康上の問題がなく、通常のキャットフードをしっかり食べている猫であれば、それだけで栄養がとれているので、あえて卵を与える必要はありません。食欲が落ちていて、何か栄養のあるものを与えたいという場合には、上記のことに注意してフードに少しふりかける程度の量からはじめてみるのが良いでしょう。
また、健康な猫でも、おやつ感覚で卵を与えてみたいという場合は、一日の必要摂取カロリーを越えないよう注意しましょう。
まとめ
卵は猫にとって、食べさせても良い食材ですが、鮮度と生卵に注意してできたら加熱して与えることを心がけましょう。また、無理に食べさせる必要も無いので、必要なときに、猫の栄養バランスを崩さない範囲で、上手に活用しましょう。
【関連記事】
猫の体重はどれくらいが標準?何キロからが肥満?
猫の下痢は何で起こる? 飼い主が知っておきたい原因と対策
これって猫が食べても大丈夫? 人間の食べ物で与えてNGなものとOKなものをまとめて解説!
【関連リンク】
ネコちゃんの食事(4) <注意が必要な食材>|みんなのどうぶつ病気大百科















