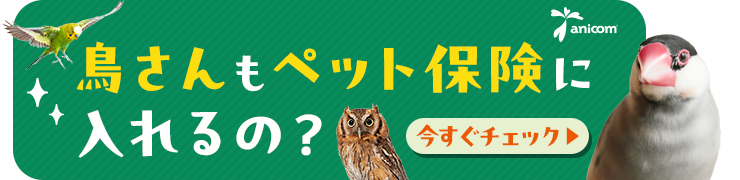「ただいま!」
玄関のドアを開けると、私より先にそう声をあげるのは、1976年生まれの、もうすぐ50歳になるわが家の大型インコ『たろう』です。緑とオレンジの鮮やかな色の羽を広げ、キョトンとした表情でこちらを見つめるその姿に、毎日癒されています。大型インコとの暮らしは、時ににぎやかで、時に想像以上に手がかかりますが、なによりも豊かで愛情深い日々を与えてくれます。
大型インコは“話す”のではなく“会話”する
「オウム返し」という言葉がありますが、大型インコたちは、ただ言葉をまねるだけではありません。こちらの問いかけにタイミングよく返してきたり、表情や状況に応じて適切な言葉を使うこともあります。
また、いろいろな芸を覚える子もいます。
わが家の『たろう』は、まるで犬のように「お手」と「おかわり」をしたり、家族の会話に割って入ったり、時には、オンライン会議中に「そうですかぁ」と急に参加してしまったりすることさえあります。
個体によっては歌を歌ったり、まるで物語を語るようにおしゃべりする子もいると聞きます。言葉を覚えるというより、飼い主との関係性の中で「伝える力」を育てていくのが、大型インコとの本当のコミュニケーションかもしれません。
大型インコとの暮らしは、“ライフスタイル”の選択

大型インコを飼うというのは、「ペットを飼う」というより「共に生きるパートナーを迎える」ことに近いかもしれません。
大型インコはとても長生きで、40年、50年、中には60年を超えて生きることもあります。つまり、人生の大半を一緒に過ごすことになるのです。私もたろうと人生のさまざまな節目を共に歩んできました。
こうなるともう「ペット」というより「同居人(鳥)」。朝は「おはよう」のあいさつからはじまり、掃除の時間になると、彼が「そろそろだよ」と言わんばかりに合図をしてくれます。
大型インコを迎える前に、知っておいてほしいこと

そんな楽しい大型インコライフですが、事前に理解しておくべき大切なポイントもあります。
1.本当に最後まで飼えますか?
大型インコの長寿は大きな魅力ですが、それは同時に大きな責任でもあります。ご自身の年齢やライフプランと照らし合わせて、最後までお世話できるのか、信頼できる引き継ぎ先があるのかなどを真剣に考える必要があります。
2.診てくれる獣医師が少ない現実
犬や猫に比べ、鳥類、特に大型インコを専門的に診られる獣医師は多くありません。
普段から健康診断を受けられる環境を整えるとともに、体調を崩したときにすぐに相談できる医療機関を見つけておくことが大切です。遠方にしか専門医がいないというケースもありますので、地域の情報収集は不可欠です。
3.声の大きさと“叫び声”の存在
見た目の可愛らしさに惹かれて大型インコを迎えた人が、最も驚くのが「鳴き声」の大きさかもしれません。
大型インコは、野生下では群れとのコミュニケーションのために大きな声を出す必要があり、その名残で、突然叫ぶように鳴くことがあります。朝方や夕方の雄叫びのような「呼び鳴き」は特に響きやすく、集合住宅や近隣環境によってはトラブルの元になることも…。
防音対策や鳴く理由の理解・対処は必須です。
4.絶滅危惧種としての一面も
美しい羽と知能の高さで人気のある大型インコですが、その多くは野生では絶滅の危機に瀕しています。
密猟や違法な輸出入が問題となっており、飼い鳥として迎える際も、法律や倫理的な面に十分配慮し、信頼できるルートから迎えることが大切です。私たち一人ひとりが責任を持った行動を取ることが、未来のインコたちを守ることにつながります。
【参考】大型インコの日本での飼育可否とワシントン条約の規制一覧
| 和名 | 英名 | 飼育可否 | 登録票の要否 | CITES附属書 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリコンゴウインコ | Blue-and-yellow Macaw | 可 | 不要 | 附属書Ⅱ | 比較的よく流通している |
| アオコンゴウインコ | Blue-throated Macaw | 可 | 要 | 附属書Ⅰ | 極めて希少。国内繁殖または過去(1983年附属書Ⅰ昇格以前)に合法輸入された個体のみ可 |
| ヨウム | African Grey Parrot | 可 | 要 | 附属書Ⅰ | 2017年COP17にて附属書Ⅰに昇格。それ以前に輸入された個体でも登録票が必要 |
| キエリボウシインコ | Yellow-naped Amazon Parrot | 可 | 要の可能性あり | 附属書ⅠまたはⅡ | 亜種によって附属書が異なるため、登録票要否も個別に確認必要 |
※ワシントン条約(CITES)の分類
- CITES附属書Ⅰ掲載種:原則輸入不可、商業目的の国際取引は禁止(国内での登録・届け出があれば飼育可能なケースあり)
- CITES附属書Ⅱ掲載種:取引可能だが輸出国・輸入国の許可証が必要
※日本での扱い
- 「特定動物リスト」の掲載有無:掲載が無い限りは原則飼育可能(鳥類は猛禽類等が該当、インコ・オウム類は含まれていない)
- 種の保存法に基づく登録制度:CITES附属書Ⅰ掲載の鳥種は、環境省発行の登録票が必要
参考:
▶経済産業省 ワシントン条約規制対象種の調べ方
▶CITES事務局のデータベースSpecies+
【関連記事】
▶【獣医師監修】ヨウムと暮らすことになったら…必要な飼育用品やお世話など飼い方ガイド|鳥との暮らし大百科
大型インコがくれた“人生の彩り”

大型インコと暮らしていると、言葉では表現しきれないような豊かな瞬間に日々出会います。朝日を浴びながらの一声、静かな夜にささやくようなおしゃべり、落ち込んだ日にはそっと寄り添ってくれるその存在。
彼らはただ「癒し」ではなく、こちらの感情を映す鏡でもあります。
長く寄り添えば寄り添うほど、相手を思いやる気持ちも深くなっていきます。
まとめ
長寿である大型インコとの暮らしは、人生を長い時間豊かに彩ってくれます。その分、知識と覚悟、そして愛情が必要です。
もしこれから大型インコを迎えたいと考えているなら、「何歳まで生きるか」「どんな環境が必要か」「誰が最後までお世話をするか」そんな未来まで見据えたうえで、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
そして、大型インコをはじめとした鳥たちが安心して暮らせる世界を、私たち人間の手で守っていきましょう。