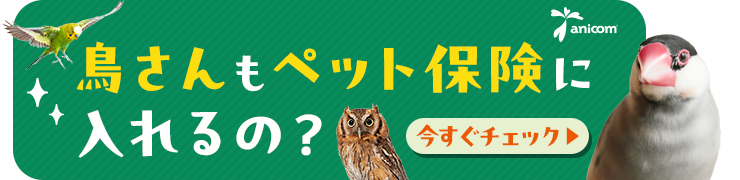
文鳥は手乗りになるほど懐いてくれる小鳥。日本では昔から飼われていて、飼育ブームが起きたこともあるほどです。今でも人気が高く、鳥飼育の初心者も飼いやすいという文鳥について、特徴や飼い方の基本を解説します。
文鳥ってどんな鳥?
文鳥は全長15cmほどの手のひらに収まるサイズの小鳥です。
インドネシア・ジャワ島の原産でスズメの仲間。英名はジャワのスズメを意味するJava Sparrowです。
日本には江戸時代初期に持ち込まれ、人気の小鳥として定着しました。昭和50年代にも飼育ブームがあり、今現在もセキセイインコと人気を二分する身近な鳥です。
文鳥の特徴は?
目の周りに「アイリング」と呼ばれる赤い輪があります。クチバシの色も赤。
野生の文鳥と同じカラーは頭が黒、頬が白、体はグレー、尾羽は黒で「ノーマル文鳥」または「並文鳥」と呼ばれます。このほか、全身が白い「白文鳥」、頭としっぽが銀灰色の「シルバー文鳥」、全体的に茶色い「シナモン文鳥」、ノーマルのカラーで頭に白い模様が入る「桜文鳥」などさまざまなカラーがあります。



文鳥はどんな性格?
人に慣れやすく、よく懐いて甘えん坊になることもあります。名前も覚えますし、懐くと手のひらに乗ってそのまま眠ってしまうことも。慣れて手のひらに乗る子は「手乗り文鳥」と呼ばれます。元気で活発な性格で運動量は多めです。
一方で、自己主張が強く、気性が荒い、怒りっぽいともいわれます。怒ってしまうと飼い主やほかの鳥を威嚇することも。この行動は弱い小鳥ゆえの警戒心の高さから起こるものといわれています。
鳴き声は?
文鳥は比較的静かな鳥で、鳴き声は小さめです。スズメと同じように「チュン、チュン」と鳴くことが多いです。発情した男の子は「ピーヨピヨピヨ」と鳴くこともありますが、あまり響くこともありません。とはいえ、鳥にとって鳴くことは大切なコミュニケーション。同じ室内にいれば、何かと鳴き声を聞くことになるでしょう。
鳴き声には種類があり、その声によって文鳥の気持ちや伝えたいことがわかります。
文鳥の寿命は?
文鳥の寿命は8年ほどといわれています。小鳥の中では長い方です。最後まで責任を持って面倒を見ることができるか、よく検討してからお迎えしましょう。
飼う前に知っておきたいこと
文鳥に限らず、小鳥は香水やアロマ、柔軟剤など香りの強いものや、調理で発生する煙で具合が悪くなることがあります。香りが強いものを文鳥がいる部屋で使わない、キッチンから遠い場所にケージを置くといった配慮が必要です。毎日のお世話も欠かせません。旅行などでお留守番させることはできないので、1日以上家を空ける場合は誰かに預けるか、世話に来てもらう必要があります。
文鳥を診てもらえる動物病院も飼う前に探しておきましょう。鳥には潜伏感染する病気もあり、症状がなくても感染症を持っていることもあります。環境変化のストレスで体調を崩すこともあるため、お迎えしたらすぐに健康診断に連れていくことをおすすめします。

文鳥の飼い方
文鳥との暮らし方や気をつけたいことを見ていきましょう。
必要な飼育用品
文鳥の飼育には次のものが必要です。
◆ケージ…一般的な小鳥のケージで飼育できます。飼育スペースに余裕があれば、なるべく広いものを用意してあげましょう。
◆止まり木…12~15mm程度の爪が浮かず、しっかり握って止まれる太さが適しています。ケージ内に高低差をつけて2ヶ所に設置し、飛び移れるようにします。
◆水入れ・エサ入れ…ケージの金網に引っ掛けるタイプが使いやすくおすすめです。ケージに付属していることもあります。洗浄や消毒をする間の予備も用意するといいでしょう。
◆おもちゃ…おすすめはブランコです。インコほど器用ではないので、かじって遊ぶタイプや足で掴んで遊ぶタイプは不向きです。
◆キャリー…通院や避難に使用するキャリーもあらかじめ用意を。
◆温湿度計…温度管理のためにケージやその近くに設置します。
◆保温器具…小鳥は寒さに弱いので、バードヒーターや保温電球、サーモスタットといった保温器具もそろえておきましょう。
◆水浴びをする器…自分で水浴びをするので、水浴び用の器(バードバス)も用意します。
水浴びは羽の汚れを落とすだけでなく、ストレス発散や運動にもなります。
文鳥が好きなタイミングでできるように、ケージの中に、毎日新しい水を入れて置いておきましょう。
上記のほか、ケージの床に敷く紙(新聞紙やキッチンペーパーなど)、掃除道具、体重測定のためのキッチンスケール、爪切りの道具なども必要になります。ケージカバーがあると、夜間にケージ内を暗くしてゆっくり休んでもらうことができます。
環境の準備
適温は20~30℃くらいです。
夏に室温が30℃を超える場合はエアコンで調整します。
逆に20℃を下回る場合は、様子を見て室温をあげるかペットヒーターなどで保温をしましょう。
日光を浴びることも必要です。日光に含まれる紫外線には、骨を丈夫にする効果があります。一日15分程度を目安に、網戸越しに日光浴をさせてあげるといいでしょう。直射日光の当たりすぎや熱中症、外気や風による冷え、脱走には注意してください。
文鳥は寂しがりやなので、ケージはリビングなどなるべく家族と一緒にいられる場所に置きましょう。
風が通るところや強い日差しが当たる場所は避けてください。
文鳥は何を食べる?
食事はペレットもしくはシード(キビやアワ、ヒエなどを混合したもの)がメインになります。シードをメインにする場合は野菜やボレー粉などを副食としてプラスします。ペレットを全く食べず、完全シード食の場合は、ビタミンやミネラル、アミノ酸などを摂取できるサプリメントも使ってあげるとよいでしょう。
慣れない食べ物は受け付けないことがあるので、飼いはじめはお迎えするショップで食べていたものと同じものを準備して与えましょう。食事内容を変更したいときは環境に充分慣れてから、様子をみながら行ってください。
お世話は何をする?
毎日のお世話はごはんを入れること(1日1回)と、お水の交換(1日2~3回)、ケージの掃除です。
掃除はケージの床に敷いた紙を交換し、フンで汚れた場所をきれいに拭き取ります。
また1日に1度、30分~1時間はケージから出して一緒に遊びましょう。活発で飼い主に甘えたい文鳥さんにとって、あまり構われないことはストレスになるので、コミュニケーションの時間もしっかりとりましょう。
お手入れは何をする?
頻度はその子によって異なりますが、爪が伸びすぎてしまう場合は爪切りが必要なことがあります。
ときには肝臓の病気や握力の低下などで爪が伸びすぎてしまうこともあるため、爪の伸びすぎが気になる場合は一度動物病院で診察を受けるのもよいでしょう。
定期的な爪切りケアも、暴れて難しい場合は動物病院でお願いすることもできます。
まとめ

文鳥は日本でも古くから人気の鳥。初心者でも飼いやすいといわれるため、初めて飼う鳥が文鳥、という人も多いでしょう。飼いやすいといわれる文鳥でも、繊細で弱い小鳥であることは変わりません。お迎えしたら毎日のお世話とコミュニケーションで体調もよくチェックし、大切に飼って文鳥との暮らしを楽しんでくださいね。













