ペットの鳥の「放鳥」とは?
飼育している鳥をケージ(鳥小屋)から出し、室内で飛ばせたり、自由な運動時間を取ってあげたりすることを「放鳥」といいます。一時保護した傷病野鳥を自然に帰す際にも「放鳥」という表現が使われることもありますが、ペットの鳥の「放鳥」は屋外に放つことはしません。かならず窓やドアを閉めて、脱走の危険がない室内空間で行います。
放鳥のメリット
屋内飼育でのケージサイズは狭くなりがち。空を飛ぶ小鳥はもちろん、チャボなどのあまり飛ばない鳥にとっても、広い空間を自由に動ける運動時間はとても大切です。
メリットは大きく分けると3つあります。
肥満と病気の予防
肥満はさまざまな病気の原因になります。高脂血症や脂肪肝動脈硬化による「心疾患」や、尿酸が身体に沈着して痛みが出る「痛風」(関節のほか、鳥には内臓痛風もあり、急死の恐れもあります)、足にタコができる「趾瘤症(しりゅうしょう:バンブルフッド)」などは、肥満によりリスクが高まると考えられます。
放鳥で運動量を確保し、また運動によって交感神経を活発に働かせることで、肥満を予防し、関連する疾病の発症リスクを下げることができます。
ストレス発散
ケージ外での運動や飼い主さんとのコミュニケーションによって、発散不足が解消されます。ストレス発散は心の健康に役立ちます。発散不足や退屈が高まると、鳥には毛引きなどの問題行動が出ることがあります。呼び鳴きやケージかじりなどの行動も発散不足があると出やすくなります。
持続発情予防
飼育下の鳥は、発情が長引きやすい傾向にあります。女の子の発情持続は過剰産卵や卵巣疾患、男の子の持続発情は精巣腫瘍などの原因になりうるため、発情を長引かせない生活環境を作ってあげたいものです。
体重管理は発情抑制のために有効な対策のひとつですが、「食事を減らしてダイエットをする」のは、鳥にとっては危険な場合もあり、獣医師との綿密な連携のもと計画的に行うのが望ましいです。
発情が長引かないように予防するという目的であれば、まずは放鳥で運動量を増やして体重が増えすぎないようにするのが良いでしょう。
放鳥中に起こりやすい事故と対策

ペットの鳥の事故は、放鳥中に起こりやすいです。ケージの外には危険がたくさんあります。飼い主自身がうっかり鳥を傷つけてしまうという悲しい事故も少なくありません。起こりやすい事故を把握し、対策をすることで、大切なわが子を守りましょう。
ドアに挟んでしまう
小鳥の羽ばたきは非常に静かなので、近くに飛んできても気づかないことがあります。そのため、放鳥中に飼い主の行動によって鳥を部屋や冷蔵庫のドアに挟んでしまう事故は珍しくありません。全身の骨折や内臓の破裂、肺挫傷など、命にかかわる重大なケガの恐れがあります。
対策
飼い主が別室への移動が必要になった時点で、一度鳥をケージに戻しましょう。ケージまでは、おやつやおもちゃなどお気に入りの物で誘導するとスムーズです。離れるのが短時間だからと油断して鳥を出したまま移動しようとすると事故が起きかねません。荷物の受け取りや飼い主のトイレなどのわずかな時間でも徹底してください。
うっかり放鳥を忘れて移動してしまわないよう、放鳥中は玄関などの出入り口に「放鳥中」の紙を貼ってもよいですね。家族が複数人いる場合は、放鳥をしているときにどうするかのルールを家庭内で共有しておきましょう。
飼い主の足やおしりで踏みつぶしてしまう
床や椅子にいた鳥に気づかず、うっかり踏んだり座ったりしてしまう事故は、即死の恐れもあり大変危険な事故です。
スマホを見ながら室内を歩いたり、テレビを見ながら椅子に腰かけたりしませんか?日常的な場所では、座面や床面をその都度確認する習慣がなくなっているものです。
対策
「ながら放鳥」をしないことです。
テレビを見ながら/通話しながら/飲食しながら……といった「ながら行動」は、放鳥中の鳥のことを忘れて、うっかり歩いたり椅子に腰かけたりしやすい状況になります。
「踏まないように見て確認しよう」という意識も大切ですが、事故はふとした一瞬に起きてしまうもの。
放鳥時間は「バードウォッチングタイム」と考え、飼い主自身の行動を制限することをおすすめします。
屋外に逃げてしまう
窓や玄関から飛び立って逃げてしまう事故です。再会できない恐れもあります。
対策
放鳥前にはすべての窓とドアが閉まっていることを確認しましょう。とくに気候が良く網戸で過ごしている季節は、網戸のズレに注意が必要です。
同居の家族がいる場合は、放鳥前の通知も忘れずに。洗濯物の出し入れなどにも気を付けてください。
また窓が閉まっていても油断は禁物。透明性の高い窓ガラスは閉まっているのがわからず、激突してしまうという事故が多くあります。脳震盪や場合によっては命にかかわることもあります。放鳥前にはカーテンを閉めておくなどして対策しましょう。
放鳥に適したお部屋は?
放鳥は安全が第一。広さより安全優先で、できるだけ鳥にとって危険なものが少ない部屋を選びましょう。
広いほど活動スペースは増えますが、ダイニングキッチンやリビングには危険なものが増えがちです。5~6畳程度の部屋でもケージよりは十分広く、放鳥が可能です。
放鳥時に注意!鳥にとって危険なもの
・飲食物
鳥が誤って口にしてしまったり、熱さでやけどをしてしまったりする恐れがあります。手からおやつを与える習慣がある場合、手に乗ろうとして手元の飲食物に入ってしまうこともありますので注意しましょう。
・家電
扇風機、炊飯器や湯沸かしポット、加湿器、電熱ヒーターなどの暖房器具などは、電源を切っておきましょう。
・目の粗いレースカーテン
爪が引っ掛かる恐れがあります。また、カーテンの重りとして鉛が使用されていることもあります。いたずらしてかじってしまうと、鉛中毒の恐れもあります。
・観葉植物
鑑賞目的の植物の多くは有毒ですが、ついばむ対象になることも。花瓶の水も植物によっては有毒になる恐れがあります。
・同居どうぶつ
ネコなどの捕食動物との同室は絶対にやめましょう。
蚊帳(かや)を使うご家庭も
ご家庭の事情にあわせて、放鳥の場所の確保のために「蚊帳(かや)」を使う飼い主さんもいます。フクロモモンガの飼育では、蚊帳の中での滑空タイムは「かやんぽ」として親しまれています。鳥に蚊帳を使う場合は、中に高さの違う止まり木を複数入れてあげて、できる限り蚊帳のネット部分に止まらなくて済むようにしてあげるといいでしょう。
小型の鳥では細い爪が蚊帳に引っ掛かって骨折などのケガをする恐れもあるので、蚊帳は確実に安全というグッズではありませんが、ご家庭の事情や鳥の種類によっては役立つかもしれません。
使用時はかならず近くで見守り、引っ掛かったときにはすぐに助けられるようスタンバイも必要です。目が粗い素材の製品や、ほつれて引っ掛かりそうな蚊帳の使用は避けましょう。
放鳥しない方がいいときは?

鳥の健康と安全のために、放鳥しない方がいいときもあります。
重度の肥満があるとき
動脈硬化がある場合、急に運動を開始すると急死する恐れがあります。
重度肥満がわかった場合は、まずは食事管理や生活環境の改善からはじめたほうが安全です。放鳥など運動開始については診察を受けた獣医師と相談してください。
体調が悪いとき
換羽中だったり、寒くもないのに膨らんでじっとしていたり、なんとなく調子が悪そうなときは、放鳥はやめておきましょう。
いつもと違う人がお世話をしているとき
ペットホテルやペットシッター、普段その子のお世話をしていない家族や友人に鳥を預けるときは、放鳥はお休みしてもよいでしょう。放鳥関連の事故を防ぐためです。お預け中は、アワ穂やフォージングトイなどのおもちゃを使って、ケージ内で楽しんでもらうのもよいですね。
万が一のケガや迷子に備えよう
100%安全な放鳥はありません。
しかし、万が一の事故を恐れて全く放鳥しないのも考えもの。ずっと狭いケージ暮らしでは、ストレスによる毛引きや、運動不足などの健康上の問題につながる可能性もあります。飼い主さんと触れあうコミュニケーションも放鳥時間の醍醐味です。ぜひ放鳥はしてあげてください。
万が一のアクシデントが起きたときに備えて、日ごろから準備もしておきましょう。
かかりつけ医を持つ・通院先を探しておく
鳥の診療が可能な病院は多くはありません。体調不良が起きてから病院を探すのでは、対応に時間がかかってしまいます。健康なときから動物病院を受診してかかりつけ医を持っておくと、緊急時もスムーズに通院しやすくなります。健康診断のほか、爪切りや糞便検査などの目的でもよいですから、元気なときから受診しておきましょう。
通院先探しにお困りの際は、以下のWebページも是非ご活用ください。どうぶつの品種(鳥)やお住まいの都道府県などを指定して、アニコム損保の窓口精算に対応している医療機関を検索できます。

※アニコム損保の窓口精算に対応していない場合等、検索結果に表示されない動物病院もあります。
※各医療機関での診療を保証するものではありません。受診前に動物病院への問い合わせをおすすめいたします。
ペット保険に加入する
鳥にケガや病気が起こった場合、家庭内でできる応急処置は少ないです。小鳥の体調不良は、様子を見ているうちにあっという間に悪化することもあります。迷わずすぐに通院できるよう、十分な治療費を用意しておきましょう。
鳥も加入できるペット保険がありますので、診療費の負担に備えて加入しておくのもよいですね。
アニコム損保のペット保険には、LINEを利用して獣医師やどうぶつの専門家に相談できる付帯サービスもあります。チャットでのオンライン相談ではスマホから動画や写真も送れます。放鳥中に起きたちょっと気になるできごとについてなども、気軽に相談ができますよ。
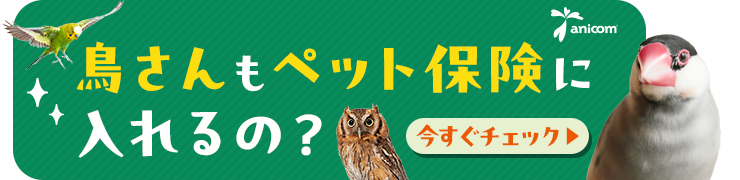
迷子になったら?
放鳥時に窓や玄関から鳥が飛んで逃げてしまうことがあります。
万が一迷子になったときには、こちらの記事を参考にして、鳥を捜索してください。
アニコム損保のペット保険に加入していると、ペット探偵による迷子捜索サービスを無料で利用できます。▶詳しくはこちら
まとめ
大好きなわが子にはたっぷり放鳥時間を楽しんでほしいですよね。
しかし、無理な放鳥をして、万が一事故が起きてしまうと、お互いにとって悲しい結末になってしまいます。
できるだけ安全な場所と時間を確保したうえで、放鳥中の鳥の生き生きした姿を見守ってあげてください。













