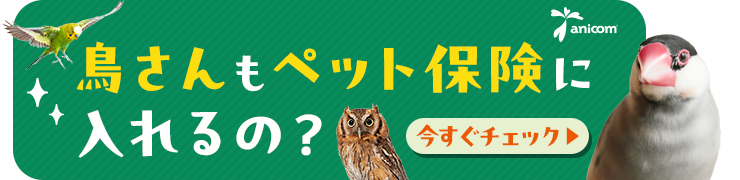
卵管蓄卵材症は、こんな病気!
卵管蓄卵材症は5歳前後の女の子の鳥にみられやすい生殖器の病気です。卵の材料である卵黄や卵白などのさまざまな物質が卵管に異常にたまり、おなかの膨れとして症状があらわれます。とくにセキセイインコに多くみられます。
「卵詰まり」は、完成した卵がうまく産卵されずに子宮部や膣部にとどまる病気ですが、「卵管蓄卵材症」は卵として完成する前の材料が、より身体の奥である卵管にたまってしまう病気です。外見的に卵の材料が溜まっていることがわかりづらく、確定診断や完治には手術が必要になることもあります。
卵管蓄卵材症になる主な原因は「性ホルモン」
卵管蓄卵材症は、発情抑制によって発症しにくくなることがわかっています。また原因となる卵が作られるのには発情周期が関わることから、発情の経験や発情過多が発症にかかわっていると推測されています。
罹りやすい年齢は3~7歳くらい、平均して5歳前後で、加齢や併発疾患の影響もあると考えられています。
卵管炎や生殖器の腫瘍、卵管の結石などによって卵管の正常な動きが妨げられた場合、未熟な卵材料が蓄積する一因になる可能性があります。
卵管蓄卵材症の主な症状は「おなかの膨らみ」
飼い主さんが気づく変化としては、おなかの膨らみが一番多いと考えられますが、食欲不振や元気がない、羽を膨らませてじっとしているなどの、一般的な体調不良のサインも表れることがあります。
完成した卵が卵の通り道でとどまってしまう「卵詰まり」は、難産に近い病態なので、いきむしぐさがでたり、おしりやおなかを触ると卵の形状が分かったりすることもありますが、「卵管蓄卵材症」は特徴的な症状に乏しい傾向にあります。膨らんだおなかを触っても、原因がなにかわからないこともあります。
卵の殻部分のかけらのようなものが溜まった場合は、稀に硬いものを感じることもありますが、全般的に触診での判断は難しいです。
卵管蓄卵材症の主な治療法は「発情管理」
診断方法
超音波検査やレントゲン検査で異常な貯留物が観察できる場合もありますが、触診や画像検査だけでは判断が難しいことも少なくありません。
液体が多く溜まっていた場合は超音波検査で、結石や砂状の卵殻がつまっていた場合はレントゲン検査で状況が把握できるケースもありますが、明確な確定診断には開腹手術を要することもあります。
治療内容
発情抑制
卵の材料が作られるメカニズムには発情が関わるので、進行を防ぐために発情をコントロールします。
発情抑制には食事管理や生活環境の整備も非常に大切ですが、治療としては確実で素早い成果も求められるため、雌性ホルモンであるエストロゲンを抑えるお薬を使うことがあります。
抗エストロゲン製剤は、経口または注射で投与します。複数回の投与が必要な場合、通院が続くこともあるでしょう。
セキセイインコは、性ホルモンの影響でロウ膜の色が変わるので(成熟した女の子は茶色や白が基本です)、抗エストロゲン製剤を使用していると、ロウ膜の色が青っぽく変化する可能性があります。
これはお薬の効き目のしくみを考えると自然なことではありますが、投薬治療中の体調変化で気になることがあれば、かかりつけ医相談しましょう。
発情が抑制されることで、徐々におなかの膨らみが改善していくこともありますが、蓄積した卵材が残ってしまう場合は、手術での根治が必要になります。
開腹手術
溜まってしまった卵材を開腹手術で摘出します。
事前に卵管蓄卵材症と推測されている場合のほか、病気がはっきりわからない場合に原因の特定をかねて手術が行われることもあります。ほかの病気での手術中にたまたま卵管蓄卵材症が判明し、そのまま摘出・治療としての手術になる場合もあります。
卵管腫瘍や卵管結石などの併発疾患があれば、それも同時に治療を行います。卵管を摘出することによって、再発予防も期待できます。
治療費の目安
超音波検査(エコー検査)、レントゲン検査を実施した場合、画像検査代がかかります。複数の画像検査を実施したり、撮影した画像の枚数が多い場合は、検査料として1万円以上かかることもあるでしょう。
発情抑制に使うホルモン剤は、投与の仕方に応じて費用が異なります。ホルモン剤を投与するにあたり、調剤料や筋肉注射での投薬の処置料などが必要になることもあります。
開腹手術の場合、治療費は高額になると考えられます。
鳥類の外科手術を実施可能な動物病院や獣医師は多くないため、治療費用の安さで病院を選ぶというよりは、通院可能なエリア内で、できる限り経験豊富で信頼できる獣医師を選ぶのがよいでしょう。治療費は動物病院によって異なるので、治療費については事前に相談すると安心です。
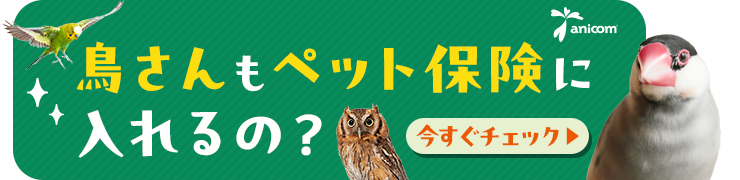
卵管蓄卵材症を予防するには
卵管蓄卵材症を予防するには、発情の管理が大切です。
発情管理を行うことで、卵管蓄卵材症の予防だけでなく、卵詰まりや体力の消耗など、さまざまな体調不良から鳥を守ることが期待できます。発情したしぐさ(例えばセキセイインコでは、尾羽を持ち上げて動かなくなる、巣作り行動をする、特有の発情臭や鳴き方をする等)が続いていたり、産卵が続いたりしている場合は、発情過多・持続発情が疑われます。普段から日記をつけて発情や産卵を記録しておくとよいでしょう。
発情管理のポイント
食事・体重管理
食事が豊富な季節に発情するメカニズムがある鳥種では、栄養状態が発情と関係します。
高カロリーなものを食べすぎていると、発情過多・持続発情を起こしやすくなります。とはいえ、急な減量や絶食は厳禁です。
産卵や発情が続いている場合は、今与えている食事の内容やおおよその量と一緒に体重も記録して、動物病院で栄養管理について相談するとよいでしょう。遊びながら食べられるフォージングトイを使うのもいいですね。
日照時間
種類による違いはありますが、一般的には鳥類の発情には日照時間が関係しています。
セキセイインコでは、明るい時間が長いと発情が持続しやすくなります。光の感知は目以外でも行っているので、目を閉じて寝ていても、明るい時間が長いと発情が続きやすい飼育環境になります。
明るい時間は一日10時間以内、それでも発情が続く場合は6~8時間以内にするなど、暗い時間の方が長くなるようにしましょう。
まとめ
卵管蓄卵材症は特徴的な症状が少なく、気づかないうちに身体の中で進んでしまっていることもある病気です。
発情管理によって発症リスクを減らせるので、食事や栄養、体重管理、日照時間に気をつけて飼育し、おなかの膨らみなどの変調があれば、早めに受診してください。












