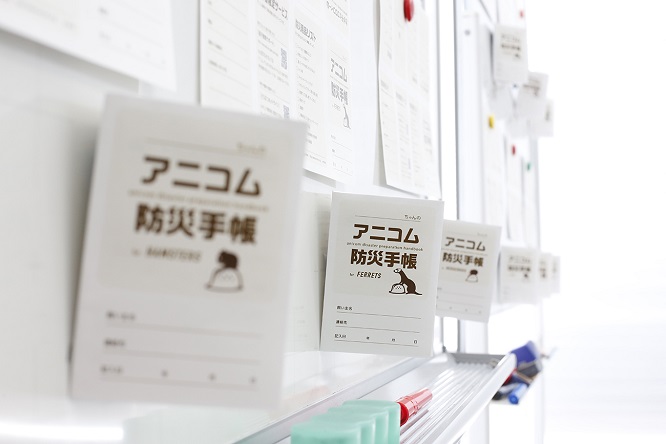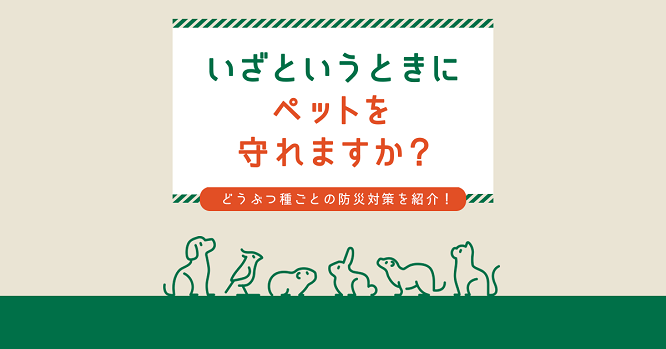どうぶつさん(ペット)との車中泊避難|準備すべきことや注意点は?
2024.01.04災害時に大切な家族であるペットと一緒に避難することは、飼い主にとって大きな課題です。
ペットとの避難については、少しずつ支援が行き届いてきたものの、避難所で生活する他の避難者の方々に気をつかい、ペットとともに車中泊避難を選択する方も多いと思います。
今回は、ペットとの車中泊避難について紹介します。
ペットとの車中泊避難のために準備しておきたいこと

●車内の環境に慣れておく
普段と違う環境は、ペットに大きなストレスを与えます。体調不良や問題行動を引き起こす原因にもなるので、日頃から車内環境に慣らしておくとよいでしょう。
また、ペットを車外に連れ出せない場合も想定して、車内で排泄ができるように練習しておくとより安心です。難しい場合はマナーウェア(おむつ)の着用も手段の一つになるでしょう。
●ペット用・飼い主用の防災用品を備えておく
防災用品は最低でも3日分、できれば1週間以上を準備することが推奨されています。ペット用・飼い主用、それぞれ準備をしておきましょう。
ペット用の防災用品は、アニコムオリジナルの防災手帳を参考に準備してみてください。
<15種のどうぶつ>
犬・猫・鳥・うさぎ・フェレット・モモンガ・リス・ハムスター・チンチラ・モルモット・ネズミ・ハリネズミ・カメ・トカゲ・ヘビ
●車外へ出てしまった時のための対策をしておく
災害時には、ペットがパニック状態に陥っている場合があります。車内の換気のため、窓やドアを開けた拍子に飛び出して迷子になってしまう恐れも…。
災害時はペットだけでなく、人間も混乱しているので、いつも以上にペットを探しにくい状況となることが想像できます。もしもの時のために、対策をしておきましょう。
<マイクロチップを装着しておく>
マイクロチップは、体に害を及ぼさないガラスで覆われたカプセル状で、チップにはそれぞれに世界で唯一の15桁の数字が記録されています。専用器具でその数字を読み取り、飼い主が指定登録機関に登録したデータと照合することで、ペットの身元を明らかにすることができます。
▶【装着している?メリットは?】マイクロチップについて、飼い主さんに聞いてみました!
<迷子札をつけておく>
親切な方がペットを見つけてくれた時に、ペットの名前・飼い主の連絡先(電話番号など)が明記された迷子札をつけていることで、再会の可能性が高まります。
<迷子ポスターを作っておく>
いなくなった場所の近くにポスターを貼ることもペットの捜索に有効です。実際に貼る場合、ポスターに掲載する個人情報や、貼る場所について確認してから貼りましょう。
<ペットの情報をまとめておく>
ペットの特徴やマイクロチップ番号など、いざという時にまとまって記載されているものがあると安心です。アニコムオリジナルの防災手帳をぜひご活用ください。
●車中泊ができる場所を確認する
車中泊は自宅の駐車場や、自治体が車中泊用に解放しているエリアで行いましょう。また、事故や盗難などの事件を防ぐため、傾斜地や人気のない場所は避けましょう。
●ガソリンは基本的に満タンにしておく
ガソリン不足では、エアコンやバッテリー充電といった車ならではの機能を活用できません。基本的に満タンにしておく習慣をつけておくことをおすすめします。また、災害発生時は、ガソリンスタンドが営業できず、ガソリン不足に陥る可能性があります。ペットのためにも日頃から備えておきましょう。
ペットとの車中泊避難で注意すべきこと

●ペットに配慮した車内環境
少しでもペットが車内で落ち着いて過ごせるように環境を整えることが大切です。
<安心できるアイテムの準備>
普段使っているベッドや毛布など、ペットや飼い主さんの匂いがついたアイテムがあると、比較的安心して過ごせます。
<車外からの視線をブロック>
外からの視線は、ペットにも飼い主さんにも、ストレスを与えます。布などで窓を覆い、目隠しをするとよいでしょう。ワンちゃんの場合、無駄吠えの防止にも役立ちます。
<トイレグッズの準備>
ペットを車外に連れ出せない可能性もあるため、車内でも排泄ができるようペットシートなどのトイレグッズも用意しておくとよいでしょう。
●ペットの脱走・迷子
ペットが車外に出て迷子にならないよう、必ずリードをつけておく、手や目を離さないなど、常に対策をしましょう。
なおアニコム損保のご契約者であれば、ペット保険の付帯サービスに「迷子捜索サポート」というサービスがあります。ペットが迷子になった場合に全国の迷子捜索ボランティア、その名も「迷子捜索隊」がペット探しをお手伝いしてくれます。必要とならないのが一番ではありますが、もしもの際はご利用ください。
※能登半島地震支援の一環として、迷子捜索サポートについて、アニコム損保のご契約者に限らずどなたでもお使いいただけるよう開放しています。対象地域は新潟県、富山県、石川県、福井県です。(2024年1月4日現在)
●熱中症・低体温症
夏期の避難の場合、熱中症に要注意です。車内にはすぐ熱気がこもるため、熱中症のリスクが高まります。窓を開けて風を通すようにしましょう。(ペットが脱走しないように注意!)
エアコンをつける場合、車内が乾燥しやすいので意識的に水分補給をしてください。
避難所の場合、トイレの数に限りがあるため水分摂取を控えておきたくなりますが、脱水状態は熱中症だけでなく、エコノミークラス症候群も発症しやすいと言われています。
ペットと一緒にこまめに水分補給をしてください。
一方、冬期は低体温症に注意が必要です。ウィンドシェードやカーテンなどを使って窓からの冷気をおさえたり、カイロや毛布で体を温めるなど防寒対策をしっかり行いましょう。
●エコノミークラス症候群
エコノミークラス症候群(ロングフライト血栓症)とは、航空機、列車、車などの狭い座席に同じ姿勢でずっと座り続けていることで起こる人の病気です。足の血流が悪くなり血のかたまり(血栓)ができ、最悪の場合、血栓が肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。
<初期症状>
足のむくみから始まり、しびれや痛み、足の一部の変色が見られます。
<予防策>
①足の位置をなるべく高くして座る
足は心臓から最も離れた部位のため、血流が滞りやすいです。荷物などの上に足を置き、足の位置を高くして、座席の背もたれをできる限り倒して血流の促進をしましょう。ミニバンやワンボックス車などでシートをフラットな状態にできる場合、就寝時はフラットにすることをおすすめします。
②こまめに立ち上がり軽いストレッチを行う
座りっぱなしを避けるため、可能であればペットと一緒に車外に出てお散歩やストレッチを行いましょう。
③こまめに水分補給を行う
上記で紹介した通り、水分補給を怠るとさまざまな健康被害が起きます。ペットと一緒にこまめに水分補給をしましょう。
なおペットがエコノミークラス症候群を発症するということは考えにくいものの、長時間同じ姿勢でいるのは身体的にも精神的にも良くありません。飼い主さんの予防策とあわせて、定期的に外の空気を吸わせてあげたり、日光浴やお散歩をしてあげましょう。
●一酸化炭素中毒
車のエンジンをつけっぱなしにして換気を怠ると、車内の空気が不足して一酸化炭素(CO)が発生します。一酸化炭素は無色・無臭なので、気づかぬうちに体調が悪くなり、死に至るケースもあります。
基本的には車のエンジンを切っておきたいですが、夏期・冬期の避難の場合、エアコンが欠かせません。エアコンをつける場合は、一酸化炭素中毒の危険性を特に意識しておく必要があります。
<初期症状>
初期症状で多く見られるのが頭痛です。一酸化炭素の濃度が上がるにつれ、判断力の低下、嘔吐、めまい、痙攣などの症状が現れます。
<予防策>
①窓を開けて換気を行う
一酸化炭素の濃度が上がらないように、定期的に窓を開けて換気を行いましょう。(ペットが脱走しないように注意!)
②車のマフラー部分がふさがらないようにする
車のマフラー部分がふさがっていると、排気ガスにより一酸化炭素中毒になる危険性があります。雪が降っている場合は特に注意が必要です。マフラー部分がふさがらないように、こまめに除雪をしましょう。何かあった時に逃げられるように、車のドア部分も除雪しておくとより安心です。
帰宅後のケアも忘れずに
避難が終わり、わが家に帰った後、ペットの健康状態を必ずチェックしましょう。ペットは本能的に体調が悪いことを隠そうとします。ペットの様子をよく観察して、健康に異変があれば、すぐに動物病院へ連れて行ってください。
さいごに
災害時にペットと車中泊をする際には、ペットの安全と快適性を確保することが重要です。
豪雨や大雪など、天候によっては車中泊すること自体が危険な場合もあるので、その時の状況に応じて適切な方法で避難しましょう。
そして2024年1月1日に発生した能登半島地震にて被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。被災地の一日でも早い復興をお祈りいたします。
公開日:2024.1.4