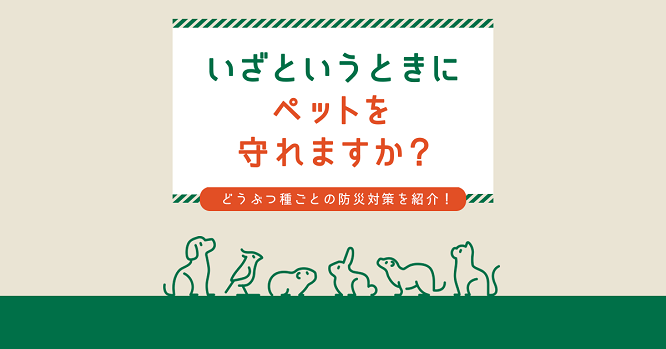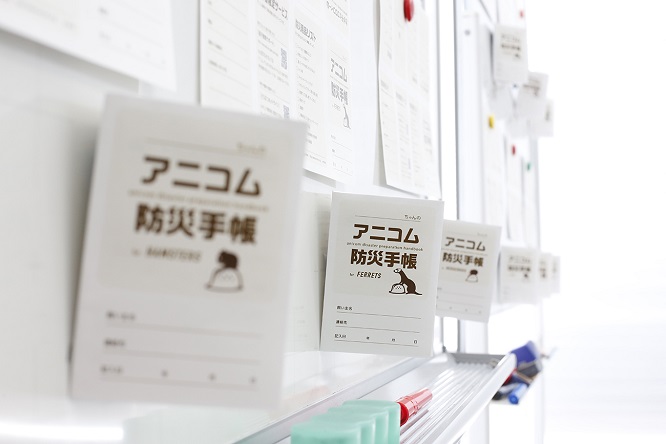
『災害時、ペットと一緒にどう動く?』第3回防災教室を開催しました!
2019.12.24『災害時、ペットと一緒にどう動く?』をテーマに開催している防災教室。
NPO法人アナイスの平井さんによる講演や避難所の運営を体験する『HUGゲーム』、アニコム社員による被災地レポートなど、災害対策に役立つコンテンツを盛り込んで開催しています。今回は、2019年11月9日に開催された第3回目のセミナーの様子をご紹介いたします。
▶第2回目の様子はこちら
「水害と台風19号」のお話し

最初に行われたのは、平井さんによる講演です。
今回は、開催の直前に台風19号が各地に多くの被害をもたらしたことから、実際に平井さんが救護活動で行かれた被災地や避難所の様子もお話しいただきました。
「地震の際は、「被災された方」が避難所へ避難します。しかし、台風などの水害の際は、被災された方だけではなく「これから被災するかもしれない方」も避難します。
そのため、収容キャパシティをオーバーしてしまう避難所もありました。運営側の課題もみえてきました。
長野市で避難所になった、とある体育館には、多くの方が避難していました。この時期の長野は夜になると寒くなりますが、天井が高い体育館では、灯油ストーブが用意されていても、すぐそばにいないと暖をとることができませんでした。
また、屋内が乾燥していたため、インフルエンザなどの感染症対策として加湿器も手配されていましたが、やはり広い体育館内では効果が期待できませんでした。
このような事例を教訓にすると、避難所以外に避難できる場所がないか、避難所生活で活用できるものはないか、あらかじめ検討しておくことも「飼い主力」や「防災力」の一つになります。」
今回、防災教室に参加された方の中には、避難所以外の避難先を検討されている非常に飼い主力の高い方もいらっしゃいました!
避難する先は、指定された避難所だけではなく、高台にある知人や親戚のお家、立体の駐車場、避難所の自転車置き場などいろいろ選択肢があることを改めて知りました。被災してから避難先を探すことは難しいため、普段からどんな選択肢があるのかを考えておくことが自分を守ることにもつながります。
避難所でのどうぶつとの過ごし方

続けて、平井さんから「避難所では、集まった被災者が積極的に協力し合うことが大切」「どうぶつ好きな方への対応」など、避難所を運営する際のポイントと、実際の避難所の様子についてお話がありました。
どうぶつが好きだから、つい触ってしまったり、食べてはいけないものをあげてしまったりする方への対応も考えなければならない、という新しい気づきがありました。
「犬が苦手な方のことは想像がついていましたが、犬に触りたい子どもへの対応等、考えさせられます…」と、参加者の声。
食べてはいけないものを与えられてどうぶつ達がお腹を壊すこともあるので、きちんと守ってあげることが大切ですね。
被災地の現場から ~災害支援を経て~

アニコムからは、防災に関する取り組みをご紹介しました。熊本地震と西日本豪雨の際、被災地で行った支援活動の写真をもとに、活動の様子をお伝えしました。
「流されてきた瓦礫やひび割れた地面…。ワンちゃんの目線で見てみると、より危険なことがわかります。」
「動物病院も被害に遭い、医療機器が壊れて診察ができないこともあります。万が一に備え、近隣の動物病院をいくつか探しておきましょう」
水害のときに心配される”レプトスピラ症”というネズミが運ぶ感染症についても説明をしました。この感染症を予防する方法は”水たまりに入らないこと”です。
台風19号では多くの地域で浸水が発生し、河川が氾濫しました。台風が過ぎても台風後の濡れた土壌や水たまりで、ワンちゃんが感染する恐れがあることから、いつもの散歩コースでなく、離れた場所で散歩をしていたという方もいらっしゃったようです。
普段は気にならないことでも、災害時には気を配らなければならないことがたくさんありますね。
しつけも「飼い主力」アップになる

避難所によっては、同伴避難ができない場合もあります。
同伴避難ができるように、他の方からの理解を得るためにも、飼い主が「飼い主力」を高めて備えておくことがとても重要です。防災グッズなどの物をそろえるだけではなく、避難先の選択肢を増やしたり、しつけをしたりすることも飼い主さんの愛情なのではないでしょうか。
今回の防災教室に応募をいただく中で、クレートトレーニングなどのしつけに関する不安の声もいただきました。「どうぶつ防災図鑑」では、防災に役立つしつけについても記事を掲載していますので、ぜひご覧いただき「飼い主力」を高めるツールにしてください。
アニコムは、今後も防災に関する取り組みを続け、情報発信に努めてまいります。
公開日:2019.12.24