治療、そして予防でも、どうぶつとの生活の中で「薬を与えること」は欠かせません。
「言葉が通じたら、薬が必要だということを理解してくれるのに」と思ったり、投薬を嫌がる犬を見て胸が痛んだりした経験のある方も多いのではないのでしょうか。
投薬をするときに大切なことは、犬の気持ちをリラックスさせることです。「薬を嫌がるのでは・・・」という飼い主さんの先入観や緊張が犬に伝わってしまわないように、まずは飼い主である私たちが正しい投薬の知識を持ち、リラックスをして飲ませることができるようにしましょう。
「嫌がっても、必要なことはしなくてはいけないのよ!」という飼い主さんの毅然とした姿勢と投薬後に犬の好きなことをしてあげて、薬を飲むことに対するイメージを良くすることの両方が必要です。
また、「何か、嫌なことが起こるのではないか」と、犬は逃げようとすることが多いのですが、物理的に逃げ出せないような工夫をすることも大切かもしれません。例えば壁際に背を向けるような状態で「オスワリ」をさせて投薬する等はいかがでしょうか。
錠剤やカプセルの飲ませ方
【食べ物に包んで与える】
茹でたサツマイモ・カボチャ・ジャガイモ等、パン、チーズ等で薬を包んで与える。
<ポイント>
■噛んだときに薬の存在に気付いて、薬を出してしまわないように、そのまま飲み込むことのできるサイズにしましょう。
■食べ物の量が多過ぎると、食べ残した中に薬が残ることがあります。食べ物の量が適当になるように調節をしましょう。
■犬が最初の一口を食べたときに「何か変!」という記憶が残ってしまわないように、最初は薬を包んでいないものを与えてみます。「もっと、欲しい」という表情を見せたときに、お薬の入った物の方を与えると良いでしょう。
■普段、食事として与えているフードに混ぜてしまうと、味を嫌がった場合にそのフード自体を食べなくなってしまことがあります。主食として食べているものとは別の食材に混ぜたほうが良いでしょう。
【投薬を補助するための製品を使う】
お薬を飲むのが苦手な人間のお子さんや犬・猫用にさまざまな投薬補助製品が販売されていますので、そのような製品を使っても良いでしょう。
日ごろからどの様な製品がどこで販売されているか調べておくと安心です。
【口を開けて薬を飲ませる】
犬の口を開けて薬を飲ませる方法もあります。口を開けられることを嫌がらない様に、日ごろからスキンシップを密にとっておくようにしましょう。
<方法>
1.一方の手で犬歯の後ろあたりを持って上あごを開き、もう一方の手で下あごを持ちます。少し上を向かせるようにして口を開かせましょう。上あごを開けるとき、鼻筋を押さえてしまって呼吸が苦しくならないように気をつけましょう。
2.口の中に錠剤を入れますが、なるべく奥の位置に素早く入れます。
3.すぐに口を閉じ、鼻先を上に向け、もう一方の手でノドをなで下ろして、嚥下(えんげ)を助けます。
4.投薬後、お水を飲ませましょう。自分から飲もうとしない場合は、あらかじめシリンジやスポイトにお水を入れて用意しておいて飲ませても良いですね。
【錠剤を砕いたりカプセルを開けて粉にしたりして飲ませる】
どうしても錠剤やカプセルのままだと飲もうとしない場合には、錠剤を砕いたりカプセルを開けて薬を出したりして、食べ物やシロップなどに混ぜると良いでしょう。
(「粉薬・液剤の飲ませ方」をご参照ください。)
<ポイント>
■ 薬の種類によっては、砕いてしまうと苦くなってしまう場合(糖衣錠など)や、薬の効果や吸収に変化を与えてしまう場合があります。砕いたり、カプセルから出して与えても問題がないかを、かかりつけの動物病院さんにご確認いただくと安心です。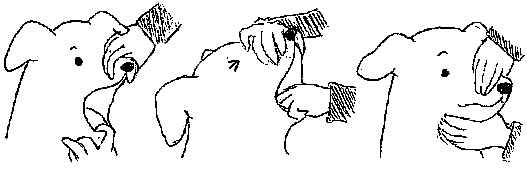
粉薬・液剤の飲ませ方
【好きなご飯に薬を混ぜて与える】
ウェットフードに混ぜ込んだり、刻んだお野菜、お肉などをお水で煮たものにお薬を混ぜて与えたりします。この時、片栗粉や葛粉でとろみを付けて与えても良いでしょう。
<ポイント>
■ 普段、食事として与えているフードに混ぜてしまうと、味を嫌がった場合にそのフード自体を食べなくなってしまことがあります。 主食として食べているものとは別の食材に混ぜたほうが良いでしょう。
■ 食べ物の量が多過ぎると、食べ残した中に薬が残ることがあります。食べ物の量が適当になるように調節をしましょう。
【スポイトや注射器を利用する】
粉薬は水で溶いて、スポイトや注射器を利用して飲ませましょう。あまり多量の水に溶かしてしまうと、すべてを飲ませるのが大変になってしまうこともあります。飲ませやすい程度の少量の水で溶かすようにしましょう。
また、一度にたくさん飲ませようとすると、薬がこぼれ出てしまうことがあります。調節をしながら飲ませましょう。水に溶かしただけでは苦くて飲もうとしない場合には、投薬用のシロップ剤(単シロップ)やガムシロップを利用すると甘くなって飲みやすくなります。
<方法>
1.粉薬の場合は少量のぬるま湯などにお薬を溶かし、スポイトなどに吸わせておきます。
2.スポイトの先を犬歯の後側に滑り込ませ、口の端から薬剤を投与します。
3.鼻先を少しあげたまま口をしばらく閉じておき、飲み込むのを見届けます。
【粉薬をオブラートに包んで与える】
粉薬を小さめのオブラートに包んで、錠剤の要領で食べ物に包んでも良いですね。水で溶いて、スポイトや注射器での投与が難しい時は、ガムシロップなどを適量加えてお団子状にしたり、練り歯磨き状の硬さに練って、上あごに塗りつけたりしても良いでしょう。
目薬のさし方
薬の容器が眼に触れないように注意をしましょう。 また容器を犬の頭上や前方から近づけると視界に入り、犬をびっくりさせることになります。なるべく視界に入らないように、目薬を後方から近づける、他のことで気をそらすなど、容器の近づけ方に注意をしましょう。
<ポイント>
■ 目の表面や周りが目ヤニなどで汚れているときは、湿らせたコットンで優しくふき取ったり、ぬるま湯を入れた洗瓶などを利用して洗い流したりして、きれいにしてから点眼しましょう。
■ 寒い時期の室温保存や冷蔵保存などで点眼薬が冷えてしまっている場合、犬に点眼したとき、冷たさにびっくりしてしまったり刺激になったりすることがあります。しばらく手で握って温めたりして人肌程度に温めてから点眼すると良いでしょう。
<方法>
1.片方の手で点眼薬を持ちます。もう一方の手で犬のあごを優しく支え、頭をやや後ろに傾けます。
2.犬の視野に薬が入らないようにするため、顔の後方から点眼薬を近づけます。
3.点眼薬を持つ手で、優しく瞼を持ち上げるようにしながら、上方から点眼します。
4.目からあふれた点眼薬をコットンなどで拭きとってあげましょう。
点眼後、犬が気にして眼をこすらないように、少しの間様子を見ていると安心ですね。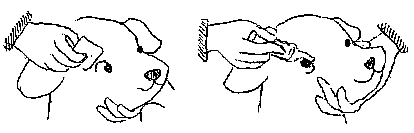
点耳薬のさし方
薬剤を投与した後は、耳道の周りを優しくマッサージして褒めてあげましょう。
<ポイント>
■ 寒い時期の室温保存や冷蔵保存などで点耳薬が冷えてしまっている場合、犬に点耳したとき、冷たさにびっくりしてしまったり刺激になったりすることがあります。
しばらく手で握って温めたりして、人肌程度に温めてから点耳すると良いでしょう。
<方法>
1.片手の、親指を犬の眼と鼻の間に置いて、他の指を下あごにあてます。もう一方の手に点耳薬を持ちます。
2.点耳薬を持った手で、少し耳を少し後ろに寝かせるようにしながら耳道に滴下します。
3.薬を置いて、耳の底部の軟骨あたりを優しくマッサージします。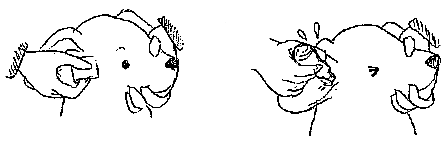
投薬に関してご注意いただきたい点
1.薬の種類によっては、一緒に投薬をしてはいけないものがあります。現在服用中の薬がある場合には注意が必要です。特にかかりつけ以外の動物病院さんの診療を受けるときは、必ず申し出るようにしましょう。
2.病気によっては摂取する食材に注意を要する場合もあります。普段食べさせていない食べ物を薬に混ぜて与える場合には、かかりつけの動物病院さんに相談していただいた方がよろしいでしょう。
3.薬の種類によって、食前・食中・食後・食間など投薬の時間を調節する必要があるものがあります。与える時間帯を誤ることで、その薬自体の吸収が充分に期待出来ない場合や、他の薬の 吸収に影響を与えしまう場合もあります。投与の時間帯に指定があるときは必ず守るようにしましょう。
4.外用薬の使用時は、外用薬を塗ったことでかえって犬が患部を気にしてしまう場合もあります。なめたりして症状を悪化させる場合もあるため、塗った後は少しの間、問題がないかを見守るようにしましょう。また、塗るタイミングを食前やお散歩前にし、犬の意識を別に向けさせることも一つの方法です。
5.投薬に慣れていなかったり、どうしても犬が暴れてしまう場合は、投薬する人と押さえる人の2人で行うと、スムーズにいくかもしれません。1人で投薬しなくてはいけない場合には、飼い主さんの体の脇を利用して保定する、タオルなどに包んで行うなど工夫をしてみましょう。
6.処方された薬の投薬が難しい場合は、かかりつけの先生に相談してみましょう。
薬の保管法について
薬の種類によって、室温保存が可能なもの、冷蔵保存が必要なもの、遮光が必要なものなどがありますので、かかりつけの獣医師さんの指示に従いましょう。
室温での保管が可能な薬剤であっても、高温・多湿・直射日光を避け、室温の変化が少ない場所で保管しましょう。
また乾燥剤と一緒に気密容器に入れて保管するとより良いでしょう。
【関連記事】
※コメント欄は、同じ病気で闘病中など、飼い主様同士のコミュニケーションにご活用ください!記事へのご意見・ご感想もお待ちしております。
※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。
お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト






アラバ、フラジール、プレドニゾロンとどうぶつさんに処方されるお薬ではございますが、どうぶつさんの状態、投与目的、投与量によっても具体的な判断が異なるため、誤飲してしまった場合は速やかに処方していただいた獣医師にご相談いただくことをお勧めします。
一般的にボミットバスター(成分:メトクロプラミド)とプレドニゾロンは必要に応じて同時に処方することもあります。しかしながら、どうぶつさんの状態、投与目的、投与量によっても具体的な判断が異なるため、処方した獣医師にもご相談いただくことをお勧めします。