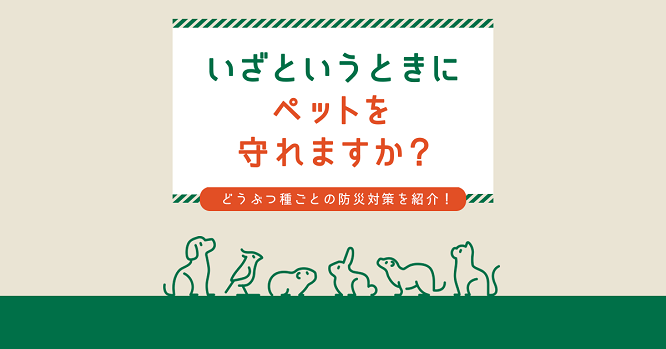被災地で活躍!災害救助犬を知ろう
2024.05.24災害が起こったとき、救助活動に参加する災害救助犬。日本でも大きな災害のたびにその活躍を耳にするようになりました。災害救助犬はどんな犬で、どのように活動しているのでしょうか。
災害救助犬って?
災害救助犬は、災害や遭難で行方不明になった人を探し出し、居場所を伝える訓練を受けた犬です。地震の被災地や土砂崩れがあった場所で活動する地震救助犬のほか、山で遭難した人を探す山岳救助犬、海や川で遭難した人を助ける水難救助犬も災害救助犬に含まれます。施設で飼育・育成される場合もありますが、ふだんは一般家庭で過ごし、ペアで活動する人(ハンドラー)は飼い主であるケースが大半です。
災害現場で
どんなことをする?
地震や土砂崩れの現場では、倒壊した建物のがれきや土砂に埋もれてしまった人の捜索を行います。1頭と1人のペアが何組か集まってチームで活動するのが基本です。災害救助犬は臭いを頼りに行方不明者を探し、見つけるとその場に座って吠えたり引っかいたりすることで居場所を知らせます。人が歩けない場所にも軽々と入り、目で見つけることができない人を見つけてくれる頼りになる存在です。ロボットなどの機械で生存者を探す技術もありますが、機械類は現場に到着してから展開するまでに時間がかかってしまいます。災害救助犬には現地入りしてすぐに活動できる、車が入りづらい現場にも行けるというメリットがあります。また緊迫した現場で作業する人や被災した人を癒す効果もあるといいます。
災害救助犬の歴史

災害救助犬のルーツは、17世紀にスイスの雪山で遭難した人を探すために訓練されていた犬たちです。発祥の地とされるスイスをはじめ、欧米で広く育成され人命救助に携わってきました。
日本では、1990年から災害救助犬の訓練を行う民間団体があらわれました。1995年に阪神淡路大震災が起こったとき、国内の災害救助犬はまだ少数でした。そしてスイスから多くの災害救助犬のチームが派遣されたにも関わらず、当時はその存在があまり認知されていなかったことから、検疫のために空港で足止めされる事態に。ようやく現場に入ったときには発生から3日が経っていて、生存者の発見率が高いタイミングを大幅に過ぎてしまいました。この出来事から災害救助犬の認知度が高まり、日本での重要性も認識されるように。以後、国内で災害救助犬を育成する団体が増えていき、現在は40ほどになっています。
国内で育成された災害救助犬は東日本大震災、熊本地震、能登半島地震などの震災で活躍し、その度に報道されました。震災を経験する度に認知度は上がっていますが、同時に課題も明らかになってきています。
災害救助犬になれるのは
どんな犬?

猟犬タイプが向いているとされますが、基本的に犬種の指定はありません。実際に活動しているのは大型犬が中心ですが、小型犬も活躍しています。小型犬には狭い隙間に入って捜索できるという強みがあります。体の大きさは関係なく、日常とは異なる災害現場でも動じずに捜索に集中できること、人を探すことを楽しめることなどが必要な素質となります。活動に適しているとされる年齢は3~8歳。8歳で引退となるケースもありますが、必要な能力が備わっていると判断されればその後も活動できる場合もあります。
災害救助犬になるには
全国で40ほどの民間団体が災害救助犬を育成する活動をしています。どこの団体でもまずは向いているかどうかチェックをし、適正があると判断されると、訓練を受けることになります。基本的な服従訓練ののち、隠れた人を探すトレーニングや、災害現場を再現した場所で人を見つける訓練を行います。その後、試験を受けて合格すると実際に災害救助犬として活動できるようになります。認定基準は日本では統一された基準はなく、各団体で作られた基準になりますが、多くは国際基準に基づいたものです。試験に合格したあとも、訓練を継続すること、定期的に試験を受け直して必要な力を維持できているか確認することが必要になります。
募集の詳細は団体により異なります。災害救助犬としての活動に興味があれば、訓練に通える範囲で募集がないか、調べてみてください。
災害救助犬の課題

日本では災害救助犬の歴史が浅く、各民間団体がそれぞれの基準で育成と活動を担っているのが現状です。今現在もいくつか課題があります。
迅速に現場に入れる体制が必要
倒壊した建物に閉じ込められた人が生存可能な時間は72時間といわれ、72時間を超えると生存率が急激に下がります。災害救助犬が不明者を発見しても、がれきの下ではすぐに救助することはできません。救助の妨げとなる屋根や柱などを取り除く作業も必要です。救助にも時間がかかるため、災害救助犬は72時間よりずっと早く現場に入り、生存者を見つけることが望まれます。
ところが、災害救助犬に関わるのは民間団体で飼い主も民間人であることから、官公庁と連携をとることが難しく、現地入りするまでに時間がかかってしまうのが現状です。海外のように災害救助犬がスムーズに活動できる体制作りが課題となっています。
訓練の精度にバラつきがある
育成する団体によって訓練の内容や認定基準が異なるため、災害救助犬の質に差が出ることも懸念されています。国内で統一した基準を作るなど、横のつながりを持って育成にあたることが期待されています。
犬の心のケア

災害救助犬が入る現場は凄惨なもの。懸命に活動しても、命を落とされた方の発見が続き、その度に現場が重い空気になることも。そんな状況では、犬たちも明らかに落ち込んでいくそうです。そこで、犬を励ますために救助者が隠れて発見させることを行います。こうして褒めてあげることで、犬の落ち込みを軽くしたり、やる気を維持したりできるのだそう。日常に戻ってからも落ち込みが続くこともあり、過酷な体験をした犬たちの心のケアも課題のひとつです。
まとめ
災害が多い日本では、災害救助犬は誰もが救われる可能性がある存在といえるでしょう。注目されるのは大きな災害が起こったときだけかもしれませんが、それまでに命を救うために地道に取り組んできた犬と人の努力があってこその成果です。今このときも、災害に備えて訓練を続けている災害救助犬たち。その力を最大限に発揮できる社会になるように、ひとりひとりができることを考えていきたいですね。
<ライター>佐藤 華奈子
公開日:2024.5.24