概要
Overview腎臓本来の機能を営む組織である実質でつくられた尿は、腎盂(じんう)と呼ばれる部分に集められます。その後、尿管を通って膀胱に貯留され、尿道を通って体外に排泄されます。この尿の流れが何らかの原因で滞り、腎盂に尿がたまって拡張した状態を水腎症といいます。進行すると腎臓の実質の部分が委縮し、腎臓の機能が低下します。
※個別のご相談をいただいても、ご回答にはお時間を頂戴する場合がございます。どうぶつに異常がみられる際は、時間が経つにつれて状態が悪化してしまうこともございますので、お早目にかかりつけの動物病院にご相談ください。
お近くの動物病院をお探しの方はこちらアニコム損保動物病院検索サイト
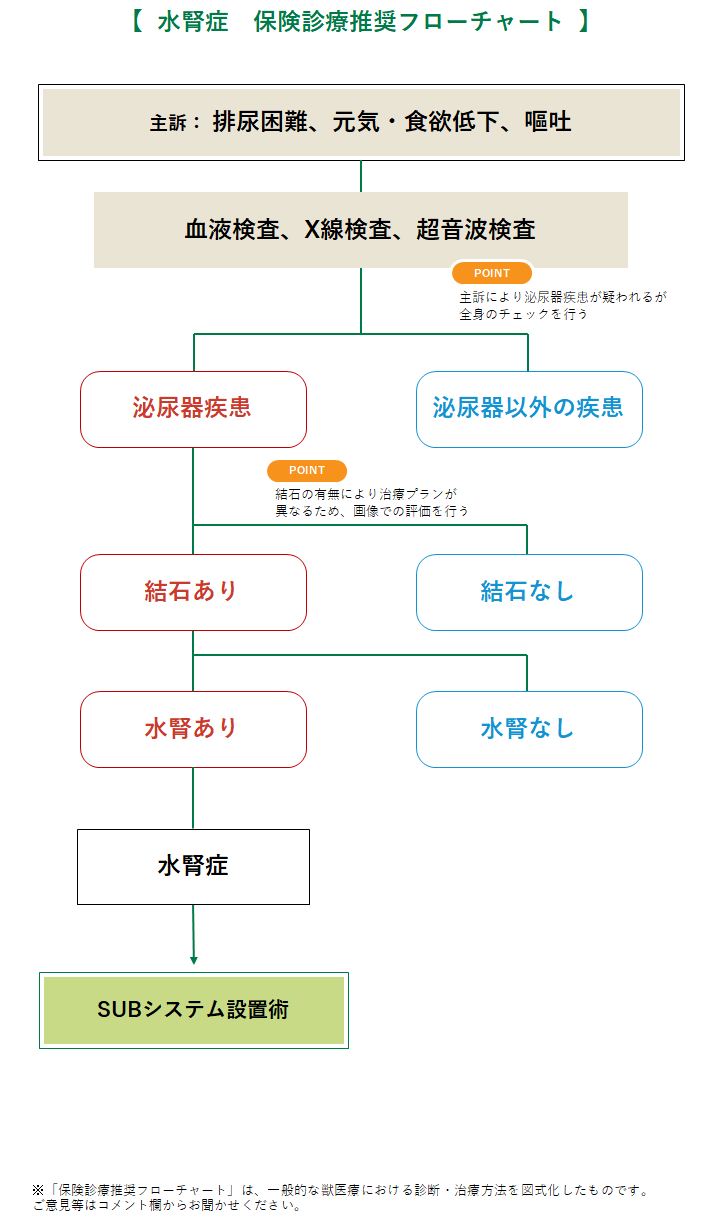
原因
水腎症には、先天性のものと後天性のものがあります。先天性の水腎症は、腎臓や尿管の奇形などによって起こります。後天性の水腎症で最も一般的な原因は尿路の閉塞であり、結石や腫瘍などによる腎臓や尿管の閉塞に続発したものが多くみられます。
その他、尿管を閉塞させるような腫瘤性の病変や外傷、尿管の手術後の合併症、子宮卵巣摘出術の際の不慮の尿管結紮(けっさつ)※ などによって発生することもあります。尿管が完全に閉塞しなくても、7~8割程度の不完全閉塞でも発生することがあるといわれています。通常は片側性ですが、尿管より下部の前立腺や膀胱、尿道の疾患に起因する尿路閉塞に続発する場合には、両側性にみられることもあります。
※糸状の組織や血管を糸などで縛る処置のことを結紮といいます。
症状
症状は閉塞の原因によって異なります。血尿、腹部や腰部の疼痛、食欲不振、発熱などがみられますが、特に症状を示さないこともあります。両側性であったり罹患していない側の腎臓の機能が低下していたりする場合には、腎不全の症状(多飲多尿、食欲不振、嘔吐、削痩※、脱水など)が見られることがあります。
※痩せてしまった状態を削痩(さくそう)といいます。
治療
どのような治療を行うかは、原因となっている疾患や腎不全を起こしているかどうかによって決定します。結石や腫瘤の摘出など、尿路の閉塞を取り除くための外科的な処置が必要となる場合もあります。早期に閉塞が解除できれば、腎臓の機能は回復することができ、予後は良好だといわれています。片側性の水腎症で、腎臓に重度の感染や腫瘍があったり、腎臓が巨大化して他の臓器を圧迫していたりする場合などは、腎摘出を検討します。腎不全の症状がある場合には、その治療を行います。
予防
定期的な健康診断(尿検査や腹部レントゲン検査、超音波検査など)を行って、尿路閉塞の原因となる疾患を早期発見、早期治療することが重要です。一般的に、尿管の閉塞が起こってから腎臓に回復不能な障害が起こるまでは2~6週間だといわれています。片側の尿管閉塞や不完全閉塞の場合には無症状、あるいは軽い症状で経過することも多いので、腎結石や尿管結石などがある犬は特に注意が必要です。また、尿路が完全閉塞を起こすと、数時間~数日という短期間のうちに急激に腎臓の機能が低下することもありますので、血尿や腹痛など気になる症状が見られたら、なるべく早く受診し、治療を受けるようにしましょう。
他の動物種のデータを見る
- 犬全体
- 大型犬
- 中型犬
- 小型犬
- アイリッシュ・ウルフハウンドってどんな犬種?特徴は?飼いやすい?
- アイリッシュ・セター
- 秋田犬
- アフガン・ハウンド
- アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- アラスカン・マラミュートってどんな犬?気を付けたい病気はある?
- イタリアン・グレーハウンド
- イングリッシュ・コッカー・スパニエルってどんな犬種?なりやすい病気は?
- イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル
- イングリッシュ・セター
- イングリッシュ・ポインター
- ウィペットってどんな犬種?気を付けたい病気はある?
- ウェルシュ・コーギー・カーディガン
- ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
- ウェルシュ・テリア
- ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア
- エアデール・テリア
- オーストラリアン・シェパードってどんな犬種なの?特徴や気を付けるべき病気は?
- オールド・イングリッシュ・シープドッグ
- 甲斐犬
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- グレート・デーン
- グレート・ピレニーズってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- ケアーン・テリア
- コリー
- コーイケルホンディエ
- ゴールデン・レトリーバー
- サモエド
- サルーキってどんな犬種?気を付けたい病気はある?
- シェットランド・シープドッグ
- 柴犬
- シベリアンハスキー
- シーリハム・テリア
- シー・ズー
- ジャック・ラッセル・テリア
- ジャーマン・シェパード・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- スキッパーキ
- スコティッシュ・テリア
- スタッフォードシャー・ブル・テリア
- セント・バーナード
- ダックスフンド(カニーンヘン)
- ダックスフンド(スタンダード)
- ダックスフンド(ミニチュア)
- ダルメシアン
- チベタン・スパニエル
- チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
- チャウ・チャウ
- チワワ
- 狆(ジャパニーズ・チン)
- トイ・マンチェスター・テリア
- ドーベルマン
- 日本スピッツ
- 日本テリア
- ニューファンドランドってどんな犬種?気を付けたい病気は?
- ノーフォーク・テリア
- ノーリッチ・テリア
- バセット・ハウンドってどんな犬種?太りやすいって本当?
- バセンジー
- バーニーズ・マウンテン・ドッグってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- パグ
- パピヨン
- ビアデッド・コリー
- ビション・フリーゼ
- ビーグル
- 外で遊ぶのが大好き!フラットコーテッド・レトリーバーってどんな犬種?
- フレンチ・ブルドッグ
- ブリタニー・スパニエル
- ブリュッセル・グリフォン
- ブルドッグ
- ブル・テリア
- プチ・バセット・グリフォン・バンデーン
- プードル(スタンダード)
- プードル(トイ)
- プードル(ミディアム)
- プードル(ミニチュア)
- プーリー
- ベドリントン・テリア
- ベルジアン・シェパード・ドッグ(タービュレン)
- ペキニーズ
- 北海道犬
- ボクサー
- ボストン・テリア
- ロシアが誇る美しい狩猟犬、ボルゾイについて|気を付けたい病気を解説!
- ボロニーズ
- ボーダー・コリー
- ポメラニアン
- ポリッシュ・ローランド・シープドッグ
- マルチーズ
- ミニチュア・シュナウザー
- ミニチュア・ピンシャーってどんな犬種?気を付けたい病気を解説!
- ヨークシャー・テリア
- ラサ・アプソ
- ラブラドール・レトリーバー
- レオンベルガーってどんな犬?気を付けたい病気はある?
- レークランド・テリア
- ロットワイラー
- ワイアー・フォックス・テリア
- ワイマラナーってどんな犬種?気を付けたい病気は?





